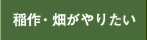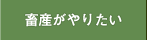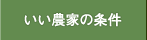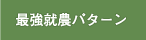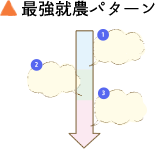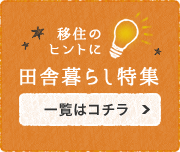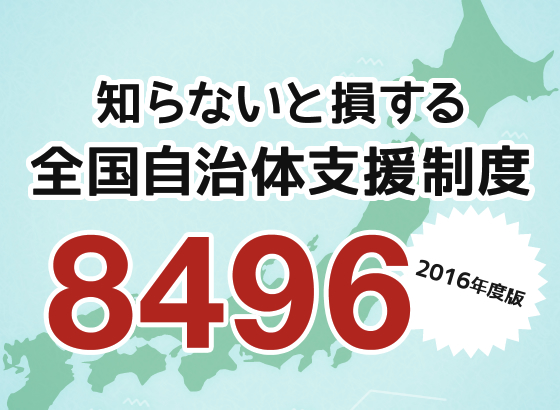- 注目の特集
- 移住したらやってみたい! 農業で食べていくための理想と現実

棚田米や田んぼアートなど、地域おこしを語るうえで欠かせない稲作。美しい稲穂をみると日本人であることの喜びを感じますね。
しかし現実としては、コメの値段は昔と比べてどんどん下がってきました。
今ではパンの消費額の方が多い家庭も増えています。稲作農家になろうと思うと、どうしても耕作面積が必要になります。
稲作農家の平均所得は、農業所得35万円、農外所得199万円、そこに年金等合わせて439万円程度だそうです。稲作の所得がとても少ないのが分かります。黒字を出すためには5ヘクタール程度の農地が必要で、農機具を買った時点でそのマイナス分を回収するために頑張らなくてはならなくなります。そして付加価値をだして、差別化することが大切になります。新潟県魚沼産や福井県池田町のコシヒカリなどは高値で売れていますが、そのような産地でノウハウを勉強するのもいいかもしれません。最初は、地元の生産組合や法人等のスタッフの一人として参画していくのが現実的だと思います。


新規参入する上で、可能性が高いのはやっぱり畑作です。畑作では何をつくるかによってずいぶん変わってきますので、事前に大まかな違いを知っておいた方が良いと思います。
それを踏まえて、「どこで、何をつくるのか」がとても大切です。JAや自治体で力を入れている品目をつくるのがまずは良いです。まずは大まかな県の主要品種を勉強するころからスタートします。関東圏でしたら、茨城のねぎ、東京でも小松菜など。神奈川の三浦半島でキャベツなども有名です。北海道ならじゃがいもやトウモロコシ、また多種多様な作物が大規模に栽培されています。関西でも京都府などでは農地が見つからないと斡旋をしないようにしていて、生活指導員がついてアフターケアがしっかりしています。また京都なら売り先は十分あります。どんなものを育ててみたいのか、漠然とでもイメージを持つと場所がぐっと選びやすくなります。また植生によって、育てやすい野菜は変わってきます。自分の愛着のある場所を先に選びその土地にあったものを育てるという方法もあります。
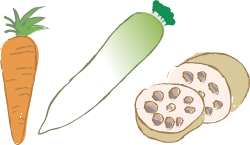
ダイコン、ニンジンなどの根菜類をつくる場合は、基本的には1年に1作が基本で、それほど頻繁に収入を得ることができません。また日持ちをする根菜では流通に時間がかかっても良いため、全国的な競争になることが特長です。

日持ちがせず、新鮮さが勝負なので、それぞれの野菜のシーズンでの競争になります。大都市にそれなりに近い方が有利になることがあります。これに対して、施設園芸ではシーズンを人工的に管理します。設備投資にお金はかかりますが、あまり出荷されていない時期に照準をあてることで、露地栽培よりも高い値が付く時期に売ることが可能になります。また、1年間に5回ほどつくることも可能で、その分しっかり収入が得
られるというメリットがあります。

長野の秋映(りんご)、山梨のデラウェア(ぶどう)、岡山のピオーネ(ぶどう)、鳥取の倉吉スイカ、長崎のさちのか(いちご)、愛媛のせとか(柑橘)なども産地を上げて、しっかりと作られています。