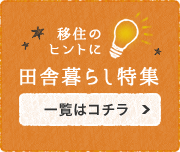-

- 注目の特集
- 地域おこし協力隊×起業 定住へのステップアップ

地域おこし協力隊は、地域との関わりを深めながら定住を目指す制度で、現在全国では7,000人以上の方々が各地域で活動しています。
また、定住に向けた道はさまざまで、仕事の選択肢も人それぞれです。
今回は、協力隊の活動をきっかけに事業を立ち上げた3組の方々にインタビューを行い、起業の経緯や地域での暮らしについてお話を伺いました。地域に根ざした働き方や定住のヒントを探ってみましょう!
3組の中にはクラウドファンディング「HIOKOSHI」を活用して起業のための支援を受けた方もいますので、気になる方は合わせてチェック!

究極にととのうリラクゼーション施設で地域活性化を目指す!
元宇宙技術者が企画・運営する「宇宙サウナ」

丸山さんの夢は宇宙飛行士で、協力隊になる前は宇宙に関する仕事をされていました。その後、協力隊として地域協力活動を行うと同時に「茶臼原ひみつのサウナ」をオープンし、2025年2月には、より快適で、さらにワクワクする体験を提供するために「宇宙サウナ」としてパワーアップさせました。
移住先として宮崎県西都市を選んだ理由は?
西都市に祖父母の家があり、幼少期に自然の中で楽しんだ思い出が今も残っています。前職を辞めていろいろ考えていた時にふとその思い出が蘇り、西都に住みたいと思ったのがきっかけです。今でも西都はとにかく自然が気持ちいいです。また宮崎市まで車で30~40分と街にも行くことができ、ほど良い田舎という点も良いところですね。
地域おこし協力隊になったきっかけは?
西都市に住もうと思って西都市のホームページを見たとき、地域おこし協力隊というものを知りました。西都市の協力隊では自治体からの命令業務と、自身で企画・実施する自主企画業務の2つを行うこととなっており、仕事の中で自分のやりたいことができることは理想的な条件でした。協力隊になった後、自主企画業務において、2023年7月に「茶臼原ひみつのサウナ」をオープンしました。
これまでやっていたサウナを「宇宙サウナ」へパワーアップした理由は?
サウナに市外のお客さんが来るようになり、運営に自信がついてきたので、自分の好きなことと経験を活かして「宇宙の旅をサウナで体感できる」をテーマにパワーアップさせました。
「宇宙サウナ」へパワーアップする際に苦労した点は?

資金調達でクラウドファンディングを活用しようと考えたとき、どのサイトにするか悩みました。今まで関わってきた人に支援をお願いする上で、支援してくださる人が安心できるサイトと考え、クラウドファウンディング最大手である㈱CAMPFIREの「HIOKOSHI」を選びました。安心と親身なサポートを提供してくれたので、当初目標金額としていた100万円を大きく上回る支援が集まりました。
今後の展望を教えてください
隊員卒業後もサウナの営業は引き続き行っていくので、「宇宙サウナ」で「宇宙とつながる」体験をぜひ味わってもらい、サウナを楽しむとともに宇宙に興味を持ってもらえるよう頑張っていきます。そして宇宙への思いは今も持ったままなので、西都市をベースにエンジニアとして活動する道も考えてはいます。また、宇宙飛行士の夢も次の募集があれば応募しようかと考えています。


事業を通じて地域を活性化する「地域商社」として
「楽しい」が続いていく地域をつくりたい

青野さんは宮崎県小林市での協力隊期間中に起業し、現在は株式会社BRIDGE the gapの代表を務められています。地域で穫れる栗を使った商品の販売や、温泉やサウナを楽しめる屋外レジャー施設「すきむらんど」の運営等、さまざまな事業を展開しています。
地域おこし協力隊になったきっかけは?
農業で起業することを考えていた時、移住相談会で小林市の担当者に話を聞き、協力隊のミッションが“起業すること”と知ったことがきっかけです。当時の小林市では足りないピースを外の力で埋めるというコンセプトで協力隊制度を始めたそうで、就業時間中の1年目3割、2年目5割、3年目7割を起業の準備にあてることができたので非常に良い環境でした。
また、任期中は、市の担当者がこちらの提案に対してどうやったら実現できるか、制度や仕組みを照らし合わせて一緒に考えてくれ、コンセプト作りから関わった「TENAMU交流スペース」も、あの体制だからこそ作れた施設だと思っています。
※TENAMU交流スペースとは?
小林まちなか複合ビル「TENAMUビル」2階にある交流スペースで、地域の方がくつろいだり、あそんだり、勉強したり、仕事をしたりできる施設となっています。
移住されて約10年とのことですが、小林市の魅力は何ですか?

住人目線でコンパクトなところです。旧中心市街地である小林駅の周辺は若い人たちが起業などのチャレンジをしていて、飲食店も多く賑わっています。そこから5分ぐらいの幹線道路沿いにはロードサイド店が広がっていて、日常の買物はそこで行っています。この2箇所を中心に小林市は円心状に田園風景が広がっており、市内のどの地区に住んでいても車を10分ぐらい走らせれば街に出ることができます。私が住んでいるところも地域の人が何故そんな田舎に住んでいるんだというところですが、車で7分ぐらいで街に行けるので不便はないです。田舎暮らしはしたいが山奥のようなところは厳しいと思う人にとっては、田舎暮らしのいいとこどりができる場所だと思います。
小林市の移住者同士のつながりは?
小林では移住者同士の横のつながりや関わりは結構ありますが、小林のいいところだと思っているのは移住者ともともと住んでいる人の線引きがあまりないところです。最近はUターンして起業する方も増えているので、移住者というよりも『新しいことをしている人』として接している人が多い印象です。
移住を考えている人にメッセージをお願いします
多くの移住者は仕事を軸に移住する場所を探していると思います。だからといって移住者を呼ぶためにIT産業のような人気が出そうな産業を誘致したりするのはちょっと違う気がしていて、その地域に根ざした産業に魅力があり、生計が成り立つようにしないといけないなと思っています。私の会社では「すきむらんど」のある須木地区の栗を使った産業を強くしようとチャレンジしています。小林市ではそういったチャレンジをしている人がいるので、そこに魅力を感じて仲間になってくれる方に来ていただけると嬉しいと思っています。

すきむらんど
住所:宮崎県小林市須木下田356番地1
- HP: https://sukimuland.com/
- Instagram: https://www.instagram.com/sukimuland/

ゲストハウス運営を通じて
「移住希望者」と「地域の人」の交流の架け橋になりたい

笹川さんは夫婦で協力隊を経験されていて、現在は二人でゲストハウス「HOSTEL LEASH」を運営されています。LEASHはお二人の共通の趣味であるサーフィンにおいて、サーフボードと足を繋ぐロープ(リーシュコード)のことで、「人と人」「人と地域」を繋ぐリーシュコードのような存在になりたいと名づけたそうです。
協力隊員時代はどんなことをされていましたか?
夫婦で移住コーディネーターとして活動し、移住希望者のサポートや地域の魅力発信に取り組みました。また、地域のイベント運営や町おこしのプロジェクトにも関わり、地域と移住希望者の橋渡し役を務めました。
現在のお仕事について教えてください

ゲストハウス「HOSTEL LEASH」を運営し、移住希望者と地域の人が交流できる場を提供しています。町の人々が利用しやすくなるよう、飲食ブースの運営にも力を入れており、立ち飲みに慣れていない人やゆっくり飲みたい人のためのテーブル席を用意しているほか、普段地域の人々が飲んでいるものとは別のお酒を置くなど、色々な工夫をしています。
起業や定住のきっかけは?
1番の決め手は海が近く、サーフィンができることですね。ここに決めるまでに海が近くにある移住候補地に滞在してみたのですが、一番しっくり来たのが川南町でした。川南町は町の人がとても親切で、快く受け入れてくれたことも大きかったです。また、移住コーディネーターとして活動する中で、地域の人と移住希望者がより自然に交流できる場が必要だと感じ、ゲストハウスの運営を決意しました。
また、ゲストハウスの準備に当たり、クラウドファンディング「HIOKOSHI」を活用しました。川南町の協力隊仲間であるパン屋さんが先にHIOKOSHIを使っていて、近くに教えてくれる人がいたので使ってみました。実際に使ってみたところサポート体制が良かったです。
今後の展望を教えてください

まずはゲストハウスの運営を安定させ、いずれ町の特産品の販売やオリジナル商品の開発にも挑戦したいです。また、サーフィンやスポーツを目的とした長期滞在者にも利用してもらえるよう、サービスを充実させていきたいです。
ゲストハウスには個室の宿泊スペースも用意していますが、8人が泊まれる共用ドミトリーをプライバシーに配慮した半個室のような形で用意しているので、ゲストハウス初心者でも利用しやすい工夫をしています。サーフィンやプロ野球の宮崎キャンプ観戦のための中長期滞在も可能なので、ぜひ遊びに来てください。

HOSTEL LEASH
住所:宮崎県児湯郡川南町川南13673番地19
今回は、地域おこし協力隊から起業し、定住へと歩む3組のストーリーを紹介しました。地域の魅力を活かした事業を展開しながら、それぞれのスタイルで暮らしを築いている姿が印象的でした。移住や起業には不安もありますが、地域とのつながりやサポートを活かせば、新たな挑戦も可能になります。今回登場した皆さんの事業は実際に訪れることができるので、興味を持った方はぜひ足を運び、地域での暮らしを体感してみてください!