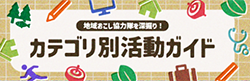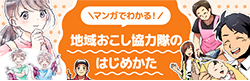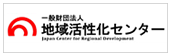応募前のリサーチ
地域おこし協力隊って何?
地域おこし協力隊は、地域の未来を応援するために、都市部から地方へ移住して地域活性化に取り組む制度です。
観光の魅力を伝えたり、農業をサポートしたりと、活動はさまざま。地域の良さを引き出し、新しい価値を生み出すのがミッションです。
最長3年間、報酬や給料をもらいながら地域社会への貢献活動を行い、自分自身の成長も期待できる制度です。
誰でも地域おこし協力隊になれるの?
地域おこし協力隊になるための特別な資格は必要ありません。ただし今住んでいる地域で隊員になることはできず、都市部から地方への移住が必須です。
自治体によっては年齢や職歴、国籍に制限がある場合や、プロジェクトごとに求められるスキルや条件がある場合も。地域ごとの活動内容をよく調べ、自分に合うプロジェクトを選ぶことが成功のカギです。
地域おこし協力隊に年齢制限はあるの?
地域おこし協力隊の制度自体には年齢制限はなく、10〜60代まで幅広い年齢層の方が活動しています。
ただし若者の移住促進が目的の場合は年齢制限があったりと、自治体によって条件はさまざまです。
しかし多くの地域では年齢より意欲や能力、地域への思いを重視しているため、遠慮しすぎる必要はありません。気になる場合は問い合わせを。
出身地の地域おこし協力隊になれるの?
地域おこし協力隊は「都市部から過疎地域などに課題解決のために必要な人材を送る」制度です。このため、現在の住民票が都市部に置かれている必要があります。
現在住んでいる場所が都市部であり、その後出身地に地域おこし協力隊としてUターンするのであれば、基本的には応募可能です。
ただし、出身者が応募できるかどうかは自治体によって異なります。応募前に募集要項をよく確認しましょう。
地域おこし協力隊になるとどんなメリットがあるの?
地域おこし協力隊になると、自分の能力や経験を活かしながら地域貢献ができるという大きなメリットがあります。新しい人間関係の中で、地方ならではの生活を体験できます。
任期中は収入が保証され、住居サポートもあるため安心して活動に専念可能。多くの自治体で任期後の起業支援制度もあり、将来のキャリアや可能性を広げるチャンスです。
地域おこし協力隊の期間は決まっているの?
地域おこし協力隊の任期は、一般的に1年から3年です。多くの場合、1年ごとの更新制で、最長3年まで活動することができます。
任期中に地域に定住することを目指して、自分の得意分野やチャレンジしたい領域でさまざまな活動を展開し、地域の課題解決に取り組みます。ただし具体的な任期は自治体によって異なるので、応募時に確認しておきましょう。
地域おこし協力隊はどんな地域で活動しているの?
地域おこし協力隊は、主に人口減少や高齢化の課題を抱える地域で活動しています。具体的には過疎地域や山村、離島、半島といった条件不利地域などで、まちのニーズに合わせた活動を展開しています。
地域おこし協力隊になると、都市部にはない自然豊かな環境や、独自の文化が残る地域で、地域の人々と協力しながら活動できるのも魅力的なポイントです。
活動中の仕事量はどれくらい?
地域おこし協力隊の仕事量は、地域やプロジェクトの内容によって異なりますが、基本的には一般的な仕事と同程度の仕事量となります。
自分自身で活動内容を企画・立案する場合も多いため、自己管理能力が求められると思っておいた方がよいでしょう。地域住民との協力や、自治体との連携を通じて、負担を調整しながら無理なく取り組むことが大切です。
地域おこし協力隊になるには移住しないといけないの?
地域おこし協力隊は都市部から過疎地域などに移住し、その場所での課題解決に向けたミッションに取り組みながら定住を図る制度です。このため、地域おこし協力隊になるには、都市部から過疎地域などへの移住(住民票の移動)が条件となります。
現在住んでいる場所と活動予定地域が同じ場合、原則応募はできません。詳細は募集要項や自治体担当者に確認してみてください。
地域おこし協力隊の制度ができた理由は?
地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化に悩む地方に、新しい風を吹き込むために生まれました。
都市部の若者や経験豊富な人材が、新鮮な視点とアイデアを持って地域に入ることで、地方の魅力を再発見し、活性化につなげることが期待されています。また、この制度は地方への移住促進や、地域と都市部の交流拡大も目指しています。
地域おこし協力隊の報酬は誰が支払ってくれているの?
地域おこし協力隊の給与は、通常受け入れ自治体から支払われます。一般的には隊員の給与や活動に必要な経費をはじめ、住宅補助などが含まれます。
ただし、地域おこし協力隊の報酬額や福利厚生は自治体ごとに異なります。応募の際に募集要項で条件を確認し、不明点があれば担当者に問い合わせておくと安心です。
地域によって活動内容はどう違うの?
活動内容は地域の特性や課題によって大きく異なります。観光振興や地域ブランディング、農業の6次産業化、空き家対策、オリジナリティあふれるユニークなプロジェクトまでさまざまです。
また同じ地域でも、協力隊員の特性や得意分野によって活動内容が変わることもあります。地域の魅力や課題を理解し、ニーズに合わせた活動を展開することが重要です。
地域おこし協力隊 活動領域マップ
https://www.iju-join.jp/section/chaosmap/
地域おこし協力隊を深堀り! カテゴリ別活動ガイド
https://www.iju-join.jp/section/category_feature/
これまでにどれくらいの人が地域おこし協力隊になったの?
地域おこし協力隊は、平成21年(2009年)の制度開始から令和5年(2023年)3月末までに、累計11,123人が任期を終了しています(※)。地域別では、北海道(1,485人)、長野県(879人)、島根県(542人)が上位となっています。
また、令和5年度には、制度開始以来最多となる7,200人の隊員が全国で活動しており、都市部と地方の交流がますます活発化しています。総務省は、2026年度までに隊員数を1万人に増やすことを目標にしており、今後さらなる広がりが期待されています。
※出典:令和5年度地域おこし協⼒隊の隊員数などについて<総務省>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000941085.pdf
地域おこし協力隊の活動内容は自分で決められるの?
活動内容は、自治体との話し合いを経て決定されます。
事前に大まかな活動分野や目標が示されることが多いですが、自分のスキルや経験、アイデアを活かした活動を展開できるのが特徴です。
ただし、地域のニーズや課題に合致した活動であることが重要なポイント。地域住民の声にしっかり耳を傾け、柔軟に活動内容を調整していくことが成功の秘訣です。
地域おこし協力隊の任期終了後、地域で活躍している事例にはどんなものがあるの?
任期終了後は、活動していた地域に定住して起業したり、地域の企業や団体に就職したりと、任期中の活動経験を生かした仕事をしている協力隊経験者がたくさんいます。
JOINのサイト内「注目の特集」にも、地域の空き家を改修してカフェレストランを開業したり、レンタルスペースを開いたりと、地域内外の人々が集う場所を生み出したインタビューを掲載しています。
地域おこし協力隊に関するセミナーやイベントでも、協力隊経験者が自身の体験を紹介している事例は多数あります。移住したい地域が決まっている場合には、募集窓口の担当者に事例を問い合わせてみることもおすすめです。
協力隊OB・OGの空き家活用紹介!
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/125/
地域おこし協力隊にはどんな支援があるの?
地域おこし協力隊には、任期中や任期終了後に活用できるさまざまな支援があります。
活動中は、自治体から住居や活動用車両の借上費、移動や研修に必要な経費、業務に必要な資格取得にかかる経費などが活動費として支給されることがあります。また、総務省や自治体が実施する研修や相談窓口を活用することも可能です。
任期終了後には、活動地域での起業を考えている場合に活用できる補助金や、定住するための空き家改修にかかる経費の支給制度などが用意されています。支援内容は自治体によって異なるため、応募時や活動中に詳細を確認しておくと良いでしょう。
地域おこし協力隊とは>利用可能な制度・サポート
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about.html#support
地域おこし協力隊が使える補助金や助成金はあるの?
地域おこし協力隊員が利用できる補助金や助成金として、以下のようなものがあります。
起業支援補助金:任期中や終了後に活動地域で起業する場合、最大100万円の補助金が支給される場合があります(総務省の財政措置による)。
活動経費補助:自治体から、活動費や備品購入費の補助が受けられる場合があります。
これらに加えて、自治体独自の補助金や助成金が設けられているケースもあります。具体的な条件や内容は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
生活費や住居のサポートはあるの?
地域おこし協力隊には、生活面でのサポートが充実しています。活動に必要な備品や交通費などが支給されることは一般的で、住居・家賃の補助があるケースも多くあります。
基本的な生活基盤のサポート体制は整っているため、安心して地域での生活を始められます。ただし具体的な支援内容は自治体によって異なるので、応募時に確認することをおすすめします。
地域おこし協力隊の給与や待遇はどうなっているの?
地域おこし協力隊の報酬は、一般的に年間約300万円程度です(高度な専門スキルを求められる場合は400万円程度)。
報酬とは別に、活動にかかる必要経費が支給される場合がほとんどです。
また、多くの自治体では住居の提供や家賃補助などの住宅サポートがある場合も多くあります。具体的な待遇については、各自治体の募集要項で確認しましょう。
地域おこし協力隊としての福利厚生(社会保険や健康保険)はどうなっているの?
地域おこし協力隊員の福利厚生は自治体によって異なり、雇用契約の有無や形態によって社会保険や健康保険の扱いが変わります。
一般的な雇用形態はフルタイムまたはパートタイムの「雇用型(会計年度任用職員)」で、地方公務員として働くため、健康保険、厚生年金、雇用保険などに加入できます。
一方、直接的な雇用契約を結ばない「委託型(個人事業主)」は国民健康保険と国民年金への加入が基本で、社会保険料は全額自己負担となります。令和5年度地域おこし協力隊に関する調査*では個人事業主の割合が全体の23%で、平成30年度調査から微増している傾向にあります。
また、上の2つ以外にも民間の企業や団体と雇用契約を結ぶ場合も全体の約1割あります。
福利厚生の詳細は自治体によって異なるため、応募前に各自治体の募集要項を確認することが重要です。
※(一社)一般社団法人 移住・交流推進機構:令和5年度地域おこし協力隊に関する調査
https://www.iju-join.jp/f-join/syousaiban.pdf
地域おこし協力隊の活動経費はどのくらい出るの?
地域おこし協力隊の活動経費は、自治体によって異なります。ただし、総務省の特別交付税措置により、隊員1人あたりの報償費等+その他の活動経費の合計は年間最大520万円が上限とされています。
【内訳】
・報償費等:最大320万円。ただし、専門性の高いスキルや経験を有する隊員、または交通条件の悪い地域で活動する隊員の場合、上限が420万円まで引き上げられることがあります。
・その他の活動経費:最大200万円。住居や活動用車両の借上費、作業道具の消耗品費、関係者間の調整に要する事務経費、定住に向けた研修費などが含まれます。隊員1人あたりの活動経費上限額は520万円なので、報酬が400万円になった場合、活動費は120万円が上限となります。
具体的な支給額や内容は自治体によって異なるため、応募前に各自治体の募集要項や担当窓口で確認しましょう。
地域おこし協力隊の必要経費はどこまでが含まれるの?
地域おこし協力隊の必要経費としてカバーされる範囲は自治体ごとに異なりますが、以下のような項目が含まれる場合が一般的です。
報償費等:活動の報酬として自治体から支払われる費用。
住宅や活動車、PCなどのリース費:活動中の住居や移動のための車、資料作成に必要なPCのリース費。
車両燃料費:活動車に必要なガソリン費。
活動に必要な旅費や交通費:現地視察や会議参加などの費用。
備品や消耗品の購入費:活動で使用する機材などの物品購入。
研修やセミナー参加費:スキルアップや地域理解を深めるための費用。
その他活動に関わる経費:住民との意見交換会や活動報告会を開催するための費用など。
必要経費の対象となる範囲や上限は自治体の規定によるため、事前に募集要項や契約内容をよく確認することをおすすめします。
地域おこし協力隊として活動中の生活費はどうなるの?
地域おこし協力隊の生活費は、自治体から支給される報償費によって賄われます。
固定費が心配な場合でも、多くの自治体では住居の家賃や活動車両の借上費が活動経費として補助されるなど、生活費の負担を軽減できる仕組みが整っています。
また、活動に必要な経費の一部(旅費や備品購入費など)は報償費とは別に支給されるため、生活費に直接影響しないよう配慮されています。
具体的な支給額や条件は自治体ごとに異なるため、応募前に募集要項や担当者に確認しておきましょう。
地域おこし協力隊として働きながら、副業はできるの?
地域おこし協力隊の副業の可否や条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
勤務時間外やフリーランス契約の場合や、任期終了後の起業・事業承継に向けた準備としての副業の場合、認められるケースもあります。
ただし本業に支障をきたさないことが前提で、具体的な条件は自治体によって異なるため、詳しくは各担当に問い合わせを。
家族やパートナー、ペットと同伴してもいいの?
家族やパートナーとの同居は基本的には問題ありません。家族での移住は地域への定着にもつながるため、多くの自治体が前向きに対応されています。事前に自治体の担当者に相談してみましょう。
ペットの受け入れについては、通常の引越しと同様、物件の広さや契約条件によって異なります。加えて地域の文化や住居の規則にも関わってくるため、特に十分確認することが大切です。
活動中に家族をサポートするための制度はある?
地域おこし協力隊として家族と共に地域に移住することになる場合、家族向けの住居を紹介してもらえるケースも多くあります。
また、活動中に出産や育児により活動を一時中断する必要がある場合には、育児や産前産後休暇のための活動中断制度の利用が可能です。その場合、最長1年間の活動中断期間が認められ、その後に活動を再開できます。
ただし、これらの制度やサポート内容は自治体ごとに異なるため、自分や家族の状況に合ったサポートが受けられるか確認しておきましょう。
家族やパートナーも一緒に地域おこし協力隊になれるの?
応募したい自治体に2名以上の隊員を受け入れる環境が整っていれば、家族やパートナーと同じ地域の協力隊員として活動することは可能です。実際に夫婦で同地域に着任された例もあります。
ただし、応募選考はそれぞれ個別に行われ、活動内容が異なる場合が多いことも覚えておきましょう。地域やタイミングによっては、家族やパートナーなど2人1組での応募大歓迎という募集もあります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
自分にぴったりの地域や活動内容を見つけるには?
自分に合った地域や活動内容を見つけ、着任後のミスマッチを事前に防ぐためには、まず自分がやりたいことや得意なこと、興味のある分野を明確にすることが大切です。以下のステップを参考に整理してみましょう。
1.自己分析をする
「どんな課題に取り組みたいか」「どんなスキルを活かしたいか」「どんな暮らしを実現したいか」「これだけは譲れないポイント」などを考え、選択の基準を明確にしましょう。募集要項に記載されているプロジェクトの目的や内容、地域の環境が、自分の目指す方向性と一致しているかを確認します。
2.情報収集をする
自己分析から得られたキーワードをもとに、当サイトや自治体の募集要項、説明会、マッチングイベントなどで、各地域の特徴や募集内容を調べてみましょう。実際の協力隊員のSNSやブログから活動報告をチェックするのもおすすめです。
3.地域との接点を増やす
興味のある地域に訪問し、地域の人々と交流してみましょう。短期移住体験プログラムや自治体が実施する交流イベントに参加すると、具体的なイメージをつかみやすくなります。より現場に近い体験をするなら、おためし協力隊制度やインターン制度の利用も検討を。
4.担当者と相談する
応募を検討している自治体の担当者に直接質問し、不明点を解消しましょう。活動内容だけでなく、地域の生活環境やサポート体制について具体的に聞くことで、自分に合った地域かどうか判断しやすくなります。
以下は、2024年10月に開催された地域おこし協力隊関連セミナーの記録動画です。制度の理解や、自分に合う地域・プロジェクトを見つける参考としてぜひ一度ご覧ください。
YouTube動画:一歩踏み出すための「地域おこし協力隊入門講座」
https://www.youtube.com/watch?v=za-HYTBss0c
自分に合う地域や制度を紹介してもらえるサービスはある?
総務省が運営する東京駅近くの「移住・交流情報ガーデン」では、地域おこし協力隊を含む移住全般について専門の相談員に無料で相談が可能です。対面での相談の他、オンライン相談にも対応しています。
東京有楽町にある「ふるさと回帰支援センター」や、大阪市中央区「大阪ふるさと暮らし情報センター」でも、全国の移住相談対応を実施しており、各地域の出張相談会も開催されています。
また、各都道府県の移住相談窓口でも、地域おこし協力隊に関する情報提供を行っているケースがあります。まずは検討している地域の窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
人と話すのが苦手だけど地域おこし協力隊になれる?
地域おこし協力隊の活動では、地域の団体や地域住民と協業することが多いため、必然的にコミュニケーションの機会も多くなります。
しかし、必ずしも話し上手である必要はありません。地域おこし協力隊活動で最も求められているのは「地域の課題解決」。地域側のニーズを丁寧にヒアリングするスキル、つまり「聞き上手」であることが重要です。
同時に相手にも自己紹介と自分が地域でやりたいことを伝えながら、少しずつ信頼関係を築いていきましょう。
地域の情報はどうやってリサーチすればいい?
気になる地域があるなら、まずは「地域名×地域おこし協力隊×募集」でWeb検索してみるのがいちばん。各自治体の移住関連ページに情報が掲載されていることが多いのでチェックしてみましょう。各地域の協力隊員のブログやSNSも参考になります。
全国の情報をリサーチしたいなら、ぜひ当サイトの「地域おこし協力隊>募集情報を探す」から検索を。対面なら、東京有楽町にある「ふるさと回帰支援センター」や大阪市中央区「大阪ふるさと暮らし情報センター」を活用するのもおすすめです。
地域おこし協力隊に関連する移住相談会やセミナーも、オンライン・リアル・大小問わず全国各地で通年開催されています。「地域おこし協力隊全国サミット」という全国規模のイベントもありますので、ぜひ足を運んでみてください。
成功の秘訣は、各ツールをバランスよく利用しながら多角的に情報を収集して、その地域に興味が高まったら、実際に現地を訪れてみること。担当者や地域のキーパーソンと会えればなお良いですね。素敵な移住ライフのためにも、できることから少しずつ始めてみましょう。
地域で求められるスキルや経験にはどんなものがある?
活動内容や地域の課題によっては特定のスキルや専門知識(ITスキル、イベント運営、マーケティング、農林水産業など)が求められる場合もありますが、多くは活動を通じて学びながら進めることが可能です。
一方で、共通して重要なのは、コミュニケーション能力やお互いを尊重する姿勢、地域と一緒に課題を解決したいという意欲です。地域の文化や価値観を理解し、積極的に関わろうとする姿勢が信頼関係を築く鍵となります。
自分のスキルや興味と地域のニーズをマッチさせる方法は?
自分のスキルや興味を地域のニーズとマッチさせるには、まず自分の強みやこれまでの経験を整理し、地域おこし協力隊としてどんな活動がしたいかを明確にすることが大切です。思いついたことを書き出すことで、自分の得意分野や興味の方向性が見えてきます。
地域おこし協力隊の活動分野にどんなものがあるかを知るには、「地域おこし協力隊 活動領域マップ」も参考になります。
分野が絞り込めてきたら、募集情報をいくつかピックアップし、条件や内容を比較してみましょう。専門家の意見が欲しい場合は、総務省が設けている「移住・交流情報ガーデン」などの相談窓口を利用するのもおすすめです。
重要なのは、自分のスキルや興味を地域の課題解決にどう活かせるかを柔軟に考え、現地の人々と協力する姿勢です。疑問や不安があれば、応募前でも地域の担当者に問い合わせてOK。直接話を聞くことで地域のニーズがより詳しく理解でき、安心して次のステップに進むことができます。
地域おこし協力隊 活動領域マップ
https://www.iju-join.jp/section/chaosmap/
移住・交流情報ガーデン
https://www.iju-join.jp/join/iju_garden/
まったく未経験の業務でも興味があれば応募できるの?
基本的には、未経験でも興味があれば応募可能です。
地域おこし協力隊の募集では、特定のスキルや経験が求められる場合もありますが、多くの場合は「地域に関わりたい」「地域課題を一緒に解決したい」という意欲や姿勢が重視されます。
未経験の分野であっても、活動を通じて学びながら成長していける環境が整えられていることが多く、活動中は自治体の担当者や地域住民のサポートを受けられるため、未経験でも一人で抱え込む必要はありません。
ただし、専門的な分野での人材募集の場合もあるため、まずは募集要項を確認し、地域の担当者に相談してみましょう。
応募前にお試しできる制度はないの?
多くの自治体が、地域おこし協力隊への応募を検討している人向けに短期滞在プログラムや体験ツアーを用意しています。
2泊3日程度で地域協力活動の体験ができる「おためし地域おこし協力隊」や、2週間〜3ヶ月の長期間滞在して実際の業務を行う「地域おこし協力隊インターン」ともそれぞれ利用できる期間や内容は地域によって異なるので、興味のある自治体に問い合わせてみましょう。
地域おこし協力隊になる前に利用できる!おためし・インターン制度とは?
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/117/
地域とのミスマッチを避けるために、どんなことを考えるべき?
地域とのミスマッチを避けるためには、自分の希望や目的を事前に整理しておくことはもちろん、自分のスキルや希望が応募する地域や自治体のニーズにマッチしているか?をしっかりと確認することが重要です。
いきなり応募するのではなく、現地訪問や担当者との会話を通じて、地域の課題や現状、住民の思いを事前に理解しておきましょう。
暮らしの場として活動地域の環境が、自分の希望する生き方や働き方にフィットしているかをイメージすることもミスマッチ防止につながります。疑問があれば担当者に質問しながら不安を解消しておきましょう。
着任後、万が一ミスマッチが起きてしまった際は一人で悩まず自治体の担当者に相談を。直接話しづらい場合は「地域おこし協力隊サポートデスク」も利用できます。
地域おこし協力隊サポートデスク
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/7626.html
応募する際にチェックすべきポイントは?
地域おこし協力隊に応募する際には、受け入れ団体や一緒に働く人々についての理解を深めておくことが大切です。どんな人たちと働くのか、その団体が地域課題をどのように捉えているかなどを可能な限り確認しましょう。
また、自分のスキルや興味が地域のニーズに合っているか、住居や周辺環境が自分に合うかも重要です。活動計画が明確で、卒業後のキャリア形成が考慮された募集内容であるかもチェックしましょう。
さらに、報酬や活動経費での収支が成り立つか、雇用形態や働き方が希望に合っているかも大切なポイント。その地域での協力隊経験者に話を聞き、実際の活動や卒業後の進路について知ることも役立ちます。
疑問があれば担当者に問い合わせ、不安を解消したうえで応募することがミスマッチ防止の鍵です。
持病があっても応募可能?
持病があっても、応募することは可能です。ただし、活動内容や地域の環境によっては負担が大きいことも考えられます。自分の体調や生活への影響を事前に考えておくことが重要です。
必要に応じて自治体の担当者に直接相談し、サポート体制や医療機関の状況について確認しておくと安心です。
応募するのにパソコンスキルはどれくらい必要?
パソコン技能の必要性は、活動内容によって異なりますが、多くの場合、基本的な操作スキルが求められます。
具体的には、活動報告書の作成や資料作り、メールでの連絡などで使用するケースが考えられます。SNSの運用や広報などでデザイン系ツールのスキルが求められる場合もありますが、必須とは限りません。
不安があれば応募前に担当者に活動内容や求められるスキルを確認しておきましょう。
就任時期のタイミングは決まっているの?
多くの自治体では、年度始めの4月や年度の半ばの10月の着任を想定して募集を行っていますが、地域の課題に応じて随時募集をしている自治体もあります。
また、特定のプロジェクトに合わせて募集するケースもあるので、興味のある自治体の情報を定期的にチェックすることが大切です。また着任日は応相談となっているケースもあるので、必要に応じて自治体担当者に相談してみましょう。
契約手続きで確認すべきことは?
雇用契約か業務委託契約かを確認し、契約形態による違いを把握することが重要です。会計年度任用職員として採用される場合、公務員規則に基づくルールが適用されることも確認しておきましょう。
また、報酬や活動経費についても確認が必要です。活動経費でカバーされる範囲(例:家賃、車両借上費、ガソリン代など)は地域や契約内容によって異なります。これらの条件を明確にし、不明点があれば担当者に相談を。
事前に契約書をしっかり読み、自分の活動や生活に影響するポイントを確認しましょう。
地域おこし協力隊はどんな物件に住んでいるの?
協力隊員の住居は、自治体が用意した一戸建てやアパート、空き家バンクを活用するケースなどさまざまです。自分で物件を探す際は、活動費の中から住居手当が支給されることもあります。
個人のニーズや協力隊の活動内容によっても適した住居が異なるため、自治体と相談しながら決めていくことが一般的です。快適な生活環境を整えることは活動の充実にもつながるため、まずは受入れ自治体に相談してみましょう。
物件探しは自分でやらないといけないの?
物件探しについては、自治体によってサポート体制が異なりますが、協力隊員用の住居があらかじめ用意されていたり、地元の不動産業者や空き家バンクなどの情報を紹介してくれるケースが多いようです。
どのようなサポートが受けられるか面接時に確認したり、内定後早めに担当者に相談することをおすすめします。
地域に引っ越すタイミングはいつ?
地域への引っ越しは、着任日までに完了するのが一般的です。
地域おこし協力隊として活動を開始するには、正式な委嘱を受けた後に住民票を異動することが必須となります。事前に住民票を異動してしまうと、制度上の要件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。
引っ越しや住民票異動の具体的なタイミングについては、受け入れ自治体の担当者に確認し、指示に従って手続きを進めると安心です。
応募前に地域の人や担当者と会ったり話したりする機会はあるの?
オンライン説明会や現地での相談会、移住体験ツアーなど、地域を知るチャンスは多数。
Webや書類だけで情報収集するのではなく、地域の担当者や一緒に働くメンバーと直接話す機会はとても重要です。
地域が抱いているリアルな課題や目標、求められる人材像がより具体的にイメージできるだけでなく、自分の希望や疑問を直接伝え、互いのビジョンを擦り合わせることもできます。
可能であれば納得できるまでしっかり面談を繰り返すことが、より良いマッチングにつながるコツです。
地域おこし協力隊の経費や報酬の財源はどこから来ているの?
地域おこし協力隊の経費や報償費等の財源は、国の特別交付税が主な支えとなっています。
この交付税を活用し、受け入れ自治体が活動経費や協力隊員の報酬などを支払っています。
応募プロセス
応募するための具体的なステップは?
地域おこし協力隊への応募は、主に以下の流れで進みます。
①自治体の募集情報を確認し、活動内容や条件を吟味する。
②興味のある自治体に、履歴書・活動計画書などの必要書類を提出する。
③書類選考や面接など、自治体による選考プロセスを経る。
④採用決定後、自治体から委嘱状等を受け取る。
⑤住民票を活動地域に異動する。
⑥協力隊として活動を開始する。
※地域によって必要書類や選考方法、住民票の異動時期などは異なるため、詳細は各自治体の募集要項でご確認ください。
各ステップで十分な準備と情報収集を行うことが重要です。特に募集情報の確認では、地域のニーズが、自身のスキルや希望と合致するかを慎重に検討しましょう。
面接は何回くらいあるの?
面接の回数は地域によって異なりますが、通常1〜2回程度といわれています。書類選考を通過すると、対面またはオンラインで実施されることが一般的です。
面接は志望動機や意欲をアピールするだけでなく、プロジェクト担当者と直接話す貴重な機会でもあります。事前に応募要項を読み返し、確認したいことや自分の希望を整理しておくと良いでしょう。
また、自治体によっては面接の前後に小論文の提出を求められる場合もあります。あらかじめ地域おこし協力隊として取り組みたい内容や、地域への想いを言葉でまとめる準備をしておくことをおすすめします。
とはいえ地域おこし協力隊の募集は未経験者も応募可能なケースが多く、面接では実績やスキルを確認するというより、地域活動や移住への意欲、家庭の状況、任期終了後のビジョンなどが多く問われている印象です。
リラックスしてありのままの自分で臨むことで、より良いマッチングにつながるのではないでしょうか。
応募から採用までどれくらい期間がかかるの?
一般的な転職と同様に、応募から採用決定までには約1〜3ヶ月程度かかると考えておくと良いでしょう。
応募受付後は書類選考、面接と進みますが、地域の状況や応募人数によって期間が異なる場合があります。
また、年度途中の随時募集や年度末・年度始めの募集では、採用までの期間が短くなることもあれば、長引くこともあります。応募を検討する際は、募集要項で選考スケジュールを確認した上で、あらかじめ余裕を持ったスケジュールで計画を立てておくことが大切です。
地域おこし協力隊にはどんな雇用形態があるの?
地域おこし協力隊の主な雇用形態は、以下の2つが主流となっています。
①会計年度任用職員:自治体の職員としての雇用で、最も一般的な形態です。健康保険や厚生年金、雇用保険などに加入できます。
②委託契約:自治体と業務委託契約を結ぶ形態で、個人事業主として活動します。国民健康保険と国民年金に加入する形が一般的です。
その他にも、地域の団体や企業に直接雇用されるパターンも一部あります。
雇用形態によって社会保険の加入状況や税金の扱いが異なるので、応募前に確認が必要です。また、起業を目指す場合は委託契約が適している場合もあります。自身の将来のキャリアプランに合わせて、最適な雇用形態を選択することが重要です。
着任前の引越し費用や家財購入などの費用は出るの?
一定額の範囲内であれば、引越し費用や家財購入費用が地域おこし協力隊の補助対象経費にあたるケースもあります。
ただし、補助の有無をはじめ、補助額や対象となる費用の範囲も自治体によってさまざまです。応募を検討する際は、募集要項や説明会で確認するか、直接自治体に問い合わせることをおすすめします。
着任前に研修を受ける機会はあるの?
地域おこし協力隊の着任前に研修が実施されるかは自治体によります。一部では、地域や活動内容を学ぶ研修や説明会が用意されているほか、「地域おこし協力隊ネットワーク」などを活用して協力隊経験者と顔合わせの機会が設けられることもあります。
また、「おためし地域おこし協力隊」や「地域おこし協力隊インターン」などの制度を導入している自治体では、応募前に実地体験ができるケースも。
着任前の研修やおためし制度がない場合でも、着任後に必要な知識やスキルを学ぶ研修が行われることも多いため、事前に担当者に確認しておくと安心です。
地域おこし協力隊全国ネットワーク
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
おためし・インターン制度とは?
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/117/
採用が決まってから現地での生活を開始するまでどれくらいの期間がかかるの?
採用通知から現地での生活を始めるまでの一般的な目安は1〜3ヶ月程度です。この間に自治体との事前打ち合わせをはじめ、引っ越しや住まいの確保など、移住に関わる準備を進めることになります。
自治体側が住居を用意してくれる場合もありますが、必要な手続きや移住準備にはある程度の時間がかかることを想定し、早めの準備を心がけましょう。
住民票を異動させるタイミングはいつ?
住民票の異動は、自治体から正式に委嘱を受けた後に行うのが一般的です。
地域おこし協力隊の制度では、都市地域から過疎地域等への移住が条件となっているため、着任前に住民票を移してしまうと要件を満たさず、採用が取り消しになってしまう可能性も否めません。
トラブルを避けるためにも、手続きの詳細や適切なタイミングについては、応募の際に自治体の募集要項や担当窓口で確認してください。
就任直前・直後
地域での生活費や住環境はどんな感じ?
雇用形態にもよりますが、地域おこし協力隊の報酬は月額16〜20万円程度が一般的です。自治体によって異なりますが、都市部と比べて物価が安い地域が多く、住居や活動用車両の借上費は活動費として補助の対象となる場合が多いため、生活費を抑えられる傾向にあります。
住環境の面では自然豊かな環境で暮らせる地域が多いことが魅力の一つです。具体的な生活費や住環境については、各自治体の募集要項を確認したり、担当者に問い合わせてみましょう。
運転免許は必要?
都市部や公共交通機関が充実している地域では必要ない場合もありますが、多くの活動地域では公共交通機関が限られているため、運転免許は必須であることが一般的です。
特に山間部や離島などでは車が生活の必需品となるケースが多く、活動用の車両を自治体が貸与したり、車の借上費を補助することもあります。募集要項をよく確認し、地域の交通事情について担当者に相談することをおすすめします。
地域の人々とどうやって信頼関係を築けばいい?
地域の住民も「どんな人が来てくれたんだろう?」と内心気にかけてくれています。ご挨拶はもちろんのこと、地域のお祭りやイベント、ボランティア活動などに参加し、自分のことを知ってもらうと同時に、地域のことも学んでいきましょう。
一緒に活動や協力を進める中で、お互いを尊重し合う姿勢が信頼を深める土台となります。地域によっては地元行事への参加が活動内容に含まれている場合もあります。
仕事でもプライベートでもさまざまな形で人と人とがつながり合っているのが地域の特徴。
担当者や協力隊経験者に地域のキーパーソンを紹介してもらったり、地元の人々が集まるお店や場所に通うことで、顔見知りを増やすのも効果的です。最初はお互いに緊張することもありますが、オープンな気持ちで接すれば次第に打ち解けていくはずですよ!
着任後、初期研修ってあるの?
総務省では年に複数回、地域おこし協力隊向けの実地・オンライン研修を行っています。内容は、着任1年以内の隊員に向けた初任者研修から、2年目以降のステップアップ研修、起業・事業化研修、テーマ別研修などさまざまです。
また、それぞれの地域主催で初任者研修を行っている場合もあります。初期研修の有無や内容は自治体によって異なるため、事前に確認すると安心です。
利用可能な制度・サポートはこちら
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about.html#support
着任前の心構えは?
「楽しむ気持ち」と「柔軟な姿勢」を持つことが大切です。新しい地域には、その土地ならではの文化や習慣があり、学びや発見がたくさん待っています。地域の人々を尊重し、まずは「知ること」を意識して、信頼関係を築く第一歩を踏み出しましょう。自分のことを知ってもらうことも大切です。
また、地域の課題解決には多様なアプローチが必要。相談できる相手を地域の中で見つけることが活動をスムーズに進める鍵となります。専門の相談員と直接話ができる「地域おこし協力隊サポートデスク」や「地域おこし協力隊ネットワーク」などの地域外のつながりを活用することも、心強いサポートになります。
さらに、自身の技能や経験を活かしながら、新しいスキルを習得する意欲を持つことも重要です。失敗を恐れず好奇心を持って挑戦しながら、長期的な視点で地域での生活と活動を楽しんでください。これらを意識すれば、卒業時には自身の成長を実感できるはずです。
地域おこし協力隊サポートデスクについて
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/7626.html
地域おこし協力隊ネットワーク
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
着任直後にやるべきことは?
地域の環境に慣れることが最優先です。まずは地域の文化や習慣への理解を深めるために、地元の行事やイベントに参加したり、地域のキーパーソンや住民と挨拶を交わして信頼関係を築いていきましょう。
並行して自分の活動内容や目標を整理し、受け入れ団体や自治体の担当者と相談しながら、具体的な活動計画を作成します。活動を円滑に進めるためには、地域の中で相談できる相手を見つけておくことも重要です。
また、生活インフラの手続きなども忘れずに。生活基盤を整えることも大切なポイントです。焦らずひとつずつ進めることは地域生活のスムーズなスタートにつながります。
地域おこし協力隊の「リアルな一日」はどんな感じ?
着任した業務内容によって異なりますが、地域おこし協力隊の一日は非常に多様です。役場や観光協会などの活動拠点に出勤し、担当者との打ち合わせや地域住民との交流を行う場合もあれば、農業や特産品づくりなど地域の現場で直接業務に取り組む場合もあります。さらに、地域資源の調査や課題の把握を目的としたフィールドワークを実施することもあります。
下記の特集では、令和5年時点で取材された地域おこし協力隊のリアルな一日のスケジュールが紹介されています。実際の活動内容を詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
協力隊って何をしているの?地域おこし協力隊の日常を深掘り!
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/134/
地域おこし協力隊の仕事は一人でやらないといけないの?
協力隊の仕事は必ずしも一人で行うものではありません。多くの場合、自治体の担当者や地域住民、他の協力隊員、受け入れ団体と連携しながら進めていきます。特に雇用型(具体的な活動内容があらかじめ定められている業務)の場合は、明確なプロジェクトに基づいてチームで活動することも珍しくありません。
一方、委託型(着任後に自分で具体的な活動計画を立てていく業務)の場合、活動の進行状況によっては一人で動くこともあるかもしれません。
しかし、協力隊の本質的なミッションが「地域おこし」である以上、地域の人々を巻き込み、奮い立たせることが一番重要です。そのためにも、自治体の担当者や地域のキーパーソン、地域内外の協力者と関係を築き、徐々に一緒に活動を進める体制を整えていくことが求められます。
困ったときや不安なときは、自治体の担当者や他の協力隊員、協力隊経験者に相談することで、サポートを受けられます。一人で抱え込まず、周りの人と協力しながら進めていきましょう。
地域おこし協力隊になるとどんな人達と一緒に仕事をするの?
協力隊員は、地域の多様な人々と協働しながら活動します。自治体職員と連携して行政の視点も取り入れながら、地域住民の方々と密接に関わり、地域の課題解決や活性化に取り組んでいきます。
同じ地域で活動する他の協力隊員とも協力し合い、時には他地域の協力隊員とも情報交換を行います。さらに、地域の事業者や団体、NPOなどとも協働することで、幅広いネットワークを築くことができます。
活動の成果は誰がどのように評価するの?
地域おこし協力隊の活動成果は、主に受け入れ自治体の担当者が評価します。評価の基準や方法は自治体によって異なりますが、以下の要素が考慮されると考えられます。
①活動計画に基づく目標達成度:任期中に設定された活動計画や目標に対して、どれだけ成果を上げられたかが評価の中心になります。
②地域への影響:地域課題に具体的なアプローチができているか、地域内に新たな取り組みや変化が生まれているかも重要な指標となります。
③活動の報告や記録:定期的な面談や年度ごとの活動報告書を通じて共有することが基本ですが、SNSやブログを活用して活動内容を地域外に発信し、広がりを持たせることも評価の一助になる場合があります。ただし、これらの発信は必須条件ではありません。
上記はあくまで一例です。具体的な評価基準については、着任時や活動期間中に受け入れ自治体の担当者に確認をし、認識を合わせておくことをおすすめします。
評価が気になるところではありますが、協力隊員が地域に移住し、活動を始めてくれること自体が大きな価値であり、地域課題解決への第一歩です。一人で全てを抱え込もうとせず、地域住民と「チーム」として協力しながら活動に取り組んでいきましょう。
地域での生活に順応するためのアドバイスは?
まずは自分の生活環境をしっかりと把握することが大切です。買い物ができる場所や医療機関など、日常生活に必要な環境を確認しておきましょう。
また、お気に入りのカフェや公園など、心休まる空間を探しておくとリフレッシュしやすくなります。
近隣の方々とのつながりを作るきっかけは、挨拶を通した気軽なコミュニケーション。地域のイベントがあれば積極的に参加し、まちの文化や風習に少しずつ触れていきましょう。
活動期間中
活動計画を立てる際のポイントは?
まずは、地域の現状やニーズをしっかりと理解することが大切です。自治体の担当者や地域の方々から意見を聞き、どのような課題があり、どのようなサポートが求められているかを把握することは、協力隊としての重要なミッションの一つです。計画には柔軟性を持たせ、状況の変化に合わせて修正できる余地を残しておくと良いでしょう。
また、短期的な目標と長期的な目標をバランスよく設定することもポイントです。小さな目標を段階的に設定し、進捗を確認しながら取り組むことで、成果を実感しやすくなります。
さらに、自治体職員をはじめ地域の方々と協力して計画を立てることをおすすめします。地域の意見を取り入れることで、具体的で地域に根ざした計画となり、活動を応援してくれるサポーターも増えるかもしれません。
地域に寄り添いながら、自分が取り組みたい内容と地域のニーズが一致するようなプランニングを心がけましょう。
活動期間の3年間は1年ごとに活動内容が変わるの?
基本的な活動方針は変わりませんが、1年ごとに活動計画を見直し、より具体的な内容にブラッシュアップしていくケースが一般的です。
1年目は地域に馴染み、地域住民との関係を築きながらニーズを調査することを重視し、2年目に具体的なミッションを設定し本格的な取り組みをスタートさせるといった流れです。
集大成となる3年目には、任期終了後のビジョンを見据えた目標設定を行います。活動計画は一度決めたら終わりではなく、柔軟に見直していくことが大切です。地域の状況やニーズは日々変化していくものと捉え、その都度調整しながら進めていくと良いでしょう。
地域おこし協力隊の活動成果はどうやって報告するの?
地域おこし協力隊の活動成果は、受け入れ自治体への定期的な報告として行うのが一般的。活動内容や進捗、成果、課題などをまとめた活動報告書の定期的な提出をはじめ、年度末には担当者や地域住民に向けて直接成果を発表したりと、報告の形式や頻度は地域によってさまざまです。
どのような活動報告を行えばいいか悩んだら、自治体の担当者や協力隊経験者に相談しながら業務を進めていきましょう。
地域おこし協力隊の活動を続けるモチベーションをどう維持する?
モチベーションを維持するためには、さまざまな視点から相談できる相手を見つけることが大切です。地域の担当者や協力隊経験者、同じ協力隊員同士で気軽に話せる関係を築いておくと、悩みや不安を共有しやすくなります。
また、情報交換の場を積極的に持つことも効果的です。似た目的を持つ仲間や地域の人と、お互いの取り組みやアイデアを共有し合うことで、新たな課題や解決策の発見につながっていきます。グループや活動に名前を付けると、仲間意識やモチベーションがより高まるかもしれません。
地域の人々や外部のネットワークを頼りながら、自分のペースで活動を続けていきましょう。
全国の隊員や隊員経験者とつながることができる「地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム」もぜひ活用ください(登録方法は自治体の担当者にお尋ねください)。
地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
自治体側の担当者は活動中にどんなサポートをしてくれるの?
自治体の担当者は、協力隊員が地域でスムーズに活動できるよう、さまざまな角度からサポートしてくれます。
具体的には、活動計画作成のアドバイスや計画の進捗管理、地域の行事や住民との交流の場の紹介、活動に必要な物資の手配や地域の情報提供、隊員が地域で孤立しないようフォローするなど、日常的なサポートを行っています。
また、活動の進捗や課題について相談に乗り、解決策を共に考えてくれる頼もしい存在です。他にも、スキルアップや他の協力隊員との交流機会の提供、行政支援が必要な場合の調整、任期終了後の定住や起業に向けた支援もバックアップしてくれます。
長期的な目線で支えてくれるパートナーとして、困ったことがあれば遠慮なく相談しましょう。
地域内での活動を円滑に進めるための心構えは?
地域住民が全員「地域おこし協力隊」という制度を熟知していることは稀です。
すぐに結果を求めるのではなく、地域の文化や考え方に耳を傾け、対話の積み重ねを通じて少しずつ信頼関係を築いていくことが重要。
「聞く姿勢」と「伝える姿勢」の両方を大切にすることが円滑な協力隊活動につながります。
相手の思いを理解した上で、自分の考えや活動内容を丁寧に伝えることを心がけましょう。
地域おこし協力隊になると地域でのイベントや行事に参加しないといけないの?
協力隊員としての役割の一環として地域のイベントや行事への参加を求められるケースはよくあります。
ただし、全ての行事に必ず参加しなければならないわけではなく、自治体の方針や活動内容によっても異なります。
地域のイベントや行事に参加する目的は、地域住民との交流機会を増やし、相互理解を深めること。無理のない範囲で少しずつ溶け込んでいきましょう。
活動中にトラブルがあったらどう対処するの?
活動中にトラブルが発生した場合は、一人で悩まず、早めに相談することが大切です。まずは受け入れ自治体の担当者や協力隊経験者に状況を伝え、客観的な意見やアドバイスを求めましょう。
トラブルの内容によっては、地域住民とのコミュニケーション不足が原因のことも。その場合、相手の話を丁寧に聞き、誤解を解消する姿勢が信頼回復につながります。
それでも解決が難しいときは、「地域おこし協力隊サポートデスク」など第三者機関への相談を視野に入れることをおすすめします。早めの判断と冷静な対応が、円滑な活動継続の鍵になります。
地域おこし協力隊サポートデスクについて
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/7626.html
活動中に体調を崩したらどうなるの?
活動期間中に怪我や病気などで体調を崩した場合は、無理をせず早めに自治体の担当者へ報告しましょう。雇用形態によって対応が異なりますが、雇用型(会計年度任用職員)の場合は、病気休暇や年次有給休暇などの休暇制度が利用できます。
一方で、委託型(個人事業主)では自治体によって設けられている休暇制度が異なります。
雇用形態に関わらず、長期療養が必要な場合や産前産後・育児休暇に関しては、自治体によって活動中断制度が設けられていることもあります。事前に募集要項や契約内容を確認し、万が一の際の対応を把握しておくことが安心につながります。
途中で退任することはできるの?
途中で退任することは可能ですが、慎重な判断が求められます。退任を希望する場合は、まず自治体や受け入れ団体と相談し、所定の手続きが必要です。
ただし、活動の途中終了は地域や関係者に影響を与える可能性があるため、事前に十分な話し合いを行い、理解を得ることが大切です。また、可能であれば引き継ぎなどをしっかり行い、円満な形での退任を目指しましょう。
任期中に別の地域や活動に変更できるの?
任期中の活動地域や活動内容の大幅な変更は、原則認められません。
ただし、活動中に自治体の方針変更や地域のニーズの変化などにより活動内容の見直しが行われるケースはあります。その場合、自治体の担当者と相談し、双方の合意のもとで調整することとなります。
何らかの事情で他の地域に転居したい、異なる活動への従事を希望する場合は、一度退任し、新たな募集に応募し直す必要があるのが一般的です。詳しい対応については自治体の担当者に相談しましょう。
活動計画が達成できない場合、変更や修正は可能?
活動計画が当初の予定通りに進まない場合、状況に応じて内容の調整が可能です。
地域おこし協力隊の活動は、地域のニーズや環境の変化に柔軟に対応することが求められるため、必要に応じて自治体の担当者と相談しながら見直しを行うことができます。目標の達成状況や地域の状況変化を踏まえ、担当者と協議の上で無理のない計画への見直しを行いましょう。
ただし、活動計画の大幅な変更は自治体の合意が必要になるため、定期的な進捗確認や面談を通じて、早めに相談することが大切です。
任期中にプロジェクトが終わらなかった場合、どうなる?
地域おこし協力隊の任期は最長3年間と定められており、任期中に成果が出せなかったとしても、それ自体が「失敗」と見なされるわけではありません。
プロジェクトが当初の目標に到達しなかった場合、後任の協力隊や地元団体に引き継いだり、任期終了後も引き続きプロジェクトに従事することも考えられます。
どのような対応になるかは自治体やプロジェクトの内容によって異なります。日ごろから細やかな報告・連絡・相談を通して担当者に進捗や状況を随時共有し、計画的に進めることが重要です。
活動期間中の休暇はどれくらい取れるの?
活動期間中の休暇は、受け入れ団体の規定や雇用形態によって異なります。
雇用型(会計年度任用職員)として採用される場合、週休2日制が適用され、年次有給休暇が付与されることが一般的です。自治体の規定によって休暇日数や取得条件が異なるため、採用前に確認しておくことをおすすめします。
一方、委託型(個人事業主)として契約する場合、休暇の取り方は自己裁量に委ねられます。ただし、活動の進行や受け入れ団体との契約内容によっては、調整が必要な場合もあります。
活動中に産休や育休は取れるの?
多くの自治体では、産前産後や育児に関わる休業期間を最長1年間取得できるようになっています。
事前に担当者と相談し、復職後の勤務形態やサポート体制も含めて詳細を確認しておくことをおすすめします。
活動中は確定申告が必要?
確定申告が必要かどうかは雇用形態によって異なります。
雇用型(会計年度任用職員)の場合、自治体によって「年末調整」がされていれば確定申告は不要です。ただし、副業による収入があれば確定申告が必要となりますのでご注意を。
委託型(個人事業主)の場合は、報酬が事業所得として扱われるため、確定申告が必要です。着任と合わせ、開業届や必要に応じて青色申告の申請などの手続きを検討しましょう。どちらのケースでも、活動経費や副収入の扱いが自治体ごとに異なるため、着任時に担当者へ確認しておくことをおすすめします。
活動中の昇給やボーナスはあるの?
会計年度任用職員としての雇用の場合、一会計年度を超えて継続して任用を行った場合(再度の任用)、昇給があり、 昇給後の給与額での任用となります。
また、会計年度任用職員であれば、期末手当・勤勉手当も6・12月の2回支給されます。
ボーナスや昇給の有無で活動する地域を絞り込むのはお勧めしませんが、詳細は募集要項などで確認しましょう。
任期中に資格取得の補助などはあるの?
資格取得の補助は自治体ごとに異なります。
一部の自治体では、資格取得にかかる受験料や教材費、研修費などの費用が活動費として認められたり、別の補助金を準備している場合もあります。
活動計画や自治体の支援内容を確認し、資格取得の希望がある場合は相談してみましょう。
地域おこし協力隊員同士の交流や情報共有の場はあるの?
隊員同士がつながり、情報を共有できるさまざまな環境があります。
たとえば、総務省が運営している「地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム」は、現役隊員や隊員経験者、自治体担当者など協力隊関係者を対象とした会員限定サービス。オンライン上で現役隊員が何に取り組んでいるか、先輩たちはどうやって課題を乗り越えたのかなど、リアルな話題で自由に交流できるのが魅力です。
また、移住・交流推進機構(JOIN)が運営する「地域おこし協力隊サポートデスク」では、協力隊経験者をはじめとする専門スタッフが電話やメールでご相談にお応えします。全国の協力隊の先輩とつながるきっかけとしてぜひご利用ください。
そのほか、都道府県によっては協力隊経験者を中心にしたネットワーク団体が設置されていたり、民間で運営されているグループや勉強会、交流イベントもあったりと、情報交換の場は多種にわたります。一度、WEBで検索なさってみてください。
地域おこし協力隊サポートデスク
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/7626.html
地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
任期終了を待たずに起業や事業承継をすることはできるの?
基本的には可能です。
任期2年目から任期終了後1年以内に活動地の同一市町村内で起業や事業承継を行う場合、多くの自治体では1人あたり100万円を上限とする費用が支給されます。
ただし、自治体や活動計画によっては活動の継続性や地域への貢献を重視し、計画の見直しを求められることもあり得ます。具体的な条件や手続きについては、各自治体の規定を確認したり、自治体担当者に相談してみましょう。
利用可能な制度・サポートはこちら
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about.html#support
任期終了後は起業しなければいけないの?
任期終了後に必ず起業しなければならないわけではありません。
任期終了後の進路は多様で、活動中に取り組んでいたプロジェクトを発展させて事業化する場合もあれば、地域の企業や団体に就職したり、自治体職員として地域づくりに関わり続けるケースもあります。また、個人事業主として活動を続けたり、別の地域や分野で新たな挑戦をする人もいます。
大切なのは、自分の目指すライフスタイルやキャリアプランに合わせて進路を選ぶことです。自治体によっては、任期終了後の定住支援や起業サポートを用意している場合もあるため、事前に担当者と確認しておくと安心です。
地域に残って起業する人はどれくらいいるの?
令和5年3⽉31⽇までに任期終了した隊員のうち、活動地と同⼀市町村内に定住した隊員(5,779⼈)は、約43%(2,497⼈)が起業、約37%(2,129⼈)が就業しています。※これまでに任期終了したすべての隊員の調査時点(令和5年5⽉1⽇)におけるデータより
令和5年度 地域おこし協⼒隊の隊員数等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000941085.pdf
地域で起業するためのサポートはあるの?
任期終了後に地域で起業を考える場合、自治体によっては起業支援や助成金制度が用意されています。また起業の相談窓口や専門家によるアドバイス、ビジネスプランの作成支援など、地域に根差した事業を立ち上げるための環境が整っていることも。
一部の自治体では、空き店舗の紹介や家賃補助など、より手厚いサポートを行っているケースもあります。
利用可能な制度・サポートはこちら
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about.html#support
自分の地域おこし協力隊活動を発信する場はある?
自治体の公式Webサイトや広報誌、SNSを通じて協力隊の活動を紹介している地域はもとより、協力隊自身が個人のブログやSNSで活動の様子を発信しているケースもよく見られます。
地域おこし協力隊の公式SNSでも、活動事例や隊員の紹介を定期的に投稿しているので、ぜひご覧ください。
ただし、発信の方法や内容については自治体の方針やルールがある場合も。事前に担当者に確認しておきましょう。
総務省‐地域おこし協力隊‐(Instagram)
https://www.instagram.com/mic_chiikiokoshikyouryokutai/
総務省‐地域おこし協力隊‐(Facebook)
https://www.facebook.com/chiikiokoshikyouryokutai/
総務省 地域おこし協力隊公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCI6G87dvZS3O8tcRPXVc7vg
地域で起業した事例にはどんなものがある?
平成30年4⽉1⽇〜令和5年3⽉31⽇に任期終了し、定住した隊員(4,463⼈)の起業の事例では、飲食サービス業、美術・デザイン・映像関連、宿泊業、農作物などの小売業、猪や鹿の食肉加工・販売などの6次産業、観光業、まちづくり支援業……と多種多様です。また、酒造や民宿など地元企業の事業承継の例もあります。※調査時点(令和5年5⽉1⽇)におけるデータより
地域のニーズや個人の希望も千差万別のため、起業した隊員の数だけ起業事例はあると考えてよいでしょう。
大切なのは、自分自身がどんな未来を描いているかです。自分の理想とする暮らしや将来のビジョンと、地域のニーズを掛け合わせた、オリジナリティあふれる起業プランを計画しましょう。自治体による起業支援もあるので、担当者に相談しながら進めると安心です。
令和5年度 地域おこし協⼒隊の隊員数等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000941085.pdf
活動計画はいつ誰が立てるの?
活動計画の内容や進め方は、自治体の方針や雇用形態によって異なります。
雇用型(会計年度任用職員)の場合、自治体や受け入れ団体があらかじめ具体的な計画を用意しているケースが多いです。
一方で、委託型(個人事業主)では、着任後に自治体の担当者や地域住民と相談し、自ら計画を立てることも。
事前に募集要項や面接で確認し、活動開始後は地域のニーズに応じて計画を見直しながら、柔軟性を持って取り組んでいきましょう。
任期終了後
任期終了時にはレポートなどを提出するの?
任期終了時に活動報告書や成果レポートの提出が求められることが一般的です。
文書での報告書作成のほか、地域住民に向けた活動報告会などで直接成果を発表するケースもあります。報告内容は、活動の経過、成果、課題、今後の活動についてなどさまざまです。
報告会を実施する目的は自治体によって異なりますが、隊員本人の振り返りのためはもちろん、自治体や地域住民がまちの課題を再認識するため、地域内外の参加者が今後の活動の参考にするため、報告会を通して改めて地域住民の士気を高めるためなど、さまざまなメリットが考えられます。
レポートの提出形式や必要な項目については、作成前に担当者に確認し、相談しながら進めましょう。
地域おこし協力隊の任期終了後の選択肢は?
任期終了後は、地域に定住して起業する、地元企業や自治体に就職する、新たな地域で協力隊を続ける、都市部に戻って経験を活かすなど多様な選択肢があります。
また、協力隊の経験者が多く活躍している地域プロジェクトマネージャーとして活躍する道も開かれています。自身の経験と地域のニーズを踏まえ、柔軟に進路を選べるのが魅力です。
地域での仕事探しのポイントは?
地域おこし協力隊の任期中に、さまざまな人との交流を広げ、深めておくことが大切です。地域おこし協力隊は公共的な立場でもあるため、多様な人々とつながりやすい環境にあります。自治体の担当者をはじめ、役場の他部署、他の現役隊員や協力隊経験者、地域の住民、地域内外の事業者など、あらゆる分野の人の話に積極的に耳を傾けてみましょう。その中から仕事の相談や求人の情報、さらには起業のヒントを得られる場合もあります。
地域に根付いた仕事を見つけるためには、地域の文化やニーズを深く理解することが重要です。日々の交流で得た情報や経験は、活動中はもちろん、任期終了後のキャリア形成にも大きな力となるでしょう。
任期終了後、地域に定住する場合の支援制度はあるの?
多くの自治体では、任期終了後も地域に定住してもらうための支援制度を用意しています。
たとえば、起業支援金や事業資金の補助、地域内での仕事紹介、空き家の改修費用の一部補助などが挙げられます。ただし支援内容は自治体ごとに異なるため、活動中に担当者へ相談しながら計画を立てていきましょう。
任期終了後、地域に残る場合の仕事や住居は自分で探さないといけないの?
地域おこし協力隊の任期終了後に地域に残る場合、基本的には仕事や住居を自分で探す必要があります。
しかし多くの自治体では、地域での定住や就職を支援する仕組みが用意されています。空き家を再生して住居とする場合はその改修費の一部、起業や事業承継をする場合は1人あたり上限100万円の補助金が支給されます(令和6年度現在。自治体によって、上限額が異なる場合があります)。
また、協力隊経験者向けのネットワークやコミュニティ等を活用して求人や住居に関する情報収集を行うのもおすすめです。
いずれにしても、任期終了後の住居や仕事については活動期間中から自治体担当者に相談し、計画的に進めると安心です。
地域に定住するための具体的なステップは?
地域に定住するためには、仕事の確保が重要なポイントです。地域おこし協力隊の任期が3年間と考えた場合の例として、以下を目安にしてみてください。
なお、実際のステップは任期終了後の計画によってさまざまです。自治体の担当者や地域の人々と相談しながら計画を固めていきましょう。
1.任期後の働き方を考えはじめる(任期2年目ごろから)
地域の求人情報を収集したり、起業に向けた計画を練り始める時期です。
協力隊の活動を通じて得られた経験や人脈が、任期後の働き方にどう活かせるかも併せて考えてみましょう。
2.住居の確保を計画する
現在の住居が任期終了後も利用可能か確認し、必要であれば早めに地域内での住居を探し始めましょう。自治体の定住支援制度を活用できる場合もあります。
3.定住準備を具体化する(任期3年目後半)
任期終了後の暮らしに支障が出ないよう、3年目後半にはその後の仕事や住居に関する具体的な契約や手続きを進めていきましょう。
任期終了後も地域に残る人はどれくらいいる?
令和5年3月31日までに任期終了した隊員11,123人のうち、およそ64.9%の7,214人が活動地やその近隣の市町村に定住しています(※)。
また、地域に定住しなかった人の中でも、1割以上が活動地と関わりのある地域協力活動に従事しています。
ですが必ずしも任期終了後に活動地域に定住しなければならないわけではありませんし、決して「定住しなかったら失敗」ではありません。任期終了後も地域と良い関係性を築くことができれば、それも協力隊としての大切な成果です。
活動を通じて得た経験やつながりを、それぞれの形で地域との関わりに生かしていただければ嬉しく思います。
※出典:令和5年度地域おこし協⼒隊の定住状況等に係る調査結果<総務省>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000950759.pdf
任期終了後、他の地域でまた地域おこし協力隊として働けるの?
新しい地域での募集条件を満たしている場合、任期終了後に別の自治体で協力隊として再度活動できるケースもあります。
しかしながら地域おこし協力隊制度は原則一つの地域で任期を全うすることを前提としており、応募の可否など事前に新しい地域の担当者に確認することをお勧めします。
新たな地域での活動が前回の経験をどう活かせるかも重要なポイントになるため、これまでの成果やスキルをしっかり整理しておくとよいでしょう。
任期終了後、地域に定住しなかった場合、地域とのつながりをどう続ける?
任期終了後に地域に定住しなかった場合でも、地域とのつながりを保つ方法は多数あります。
例えば、地域のお祭りやイベントに参加する、定期的に地域を訪れて地元の方々と交流する、地域のプロジェクトにリモートで関わる、SNSで地域の情報を発信する、情報交換をするなど、住んでいなくても地域活動に貢献することは十分可能です。
地域とのつながりは住む場所に限らず、多様な形で維持できるもの。何年経っても笑顔で再会できるような温かな関係を続けていけると素敵ですね。
任期終了後も地域おこし協力隊のネットワークに参加できる?
多くの場合、任期終了後も地域おこし協力隊のネットワークに参加することができます。
地域おこし協力隊制度は任期中だけでなく、任期終了後のキャリア形成や地域とのつながりも重視していることが特徴のひとつ。全国的なネットワークや地域ごとのコミュニティが整備されており、さまざまな情報の共有やビジネス連携、現役隊員のサポートなどの機会を得ることができます。
「地域おこし協力隊 全国ネットワークプラットフォーム」に参加するほか、自治体の担当者から地域のネットワークを紹介してもらうなど、自分に合った方法でつながりを広げてみてください。
地域おこし協力隊 全国ネットワークプラットフォーム
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
地域おこし協力隊としての仕事やプロジェクトを誰かに引き継ぐ必要はあるの?
任期終了時に必ず引き継ぎを求められるわけではありませんが、プロジェクトの進捗状況や地域のニーズによっては、次の協力隊員や地域の担当者への引き継ぎが必要になる場合があります。
引き継ぎの形は地域によって異なりますが、一般的には活動内容や成果、課題、今後の見通しを報告書としてまとめる形が取られると考えてよいでしょう。具体的な引き継ぎ方法については、自治体の担当者と事前に相談し、計画的に準備を進めるとスムーズです。
地域おこし協力隊で得たスキルは他の仕事にどう活かせるの?
地域の課題解決に取り組むことで、企画力や問題解決能力が磨かれ、コミュニケーション能力やリーダーシップも向上します。
また、地域資源を活用した商品開発やPR活動を行うことで、マーケティングやブランディングのスキルも身につきます。活動を通して得たスキルは、起業はもちろん、一般企業や行政、NPOなどさまざまな分野で活かすことができます。
地域おこし協力隊の制度は将来的にどう変わっていくの?
地域おこし協力隊は、総務省が地域力創造の柱として注力している重要な制度です。
令和4年(2022年)には、令和8年度(2026年度)までに現役隊員数を1万人に到達させる目標を掲げており、都市部から地方への人の流れをさらに拡大させ、地域の課題解決と持続可能な地域社会の構築に向けた取り組みの強化を図ります。
また、協力隊の活動や制度の魅力を広く伝える広報活動の強化、応募検討者が地域での暮らしや活動を事前に体験できる「おためし地域おこし協力隊」や「地域おこし協力隊インターン」の活用も進んでいます。
地域おこし協力隊の制度は、単なる短期的な施策にとどまらず、都市部の人材を継続的に地域に呼び込む仕組みづくりや、地域力の維持・強化を目指したものです。今後も、地方と都市をつなぐ未来志向の制度として進化を続けていきます。
地域おこし協力隊になる前に利用できる!おためし・インターン制度とは?
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/117/
任期終了後の人生の選択肢を広げるためのアドバイスは?
任期終了後の選択肢を広げるには、任期中に多様な経験を積むことが重要です。地域の活動に関わり幅広いスキルを身につけながら、地域内外のネットワークを広げ、信頼関係を築くことも大切です。自治体の研修や支援制度もうまく活用しましょう。
自分の強みを明確にし、起業や就職の準備を進めることで、任期終了後の選択肢が広がります。応援しています!