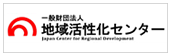Interview隊員インタビュー

川のある暮らしから、地域の未来をつくる
高知県四万十市 松本凌平さん町の人の交流から生まれた、“ここで暮らす”という感覚
神奈川県は湘南エリア、家族と穏やかな日常を送っていた松本さん。
都市と自然が共存する場所での暮らしは快適だったものの、ある時ふと「このまま同じ日々が続いていくのか」と考えるようになったといいます。
「何か大きな不満があったわけではなくて、ただ“もう少し暮らしと丁寧に向き合ってみたい”という思いが湧いてきたんです。少し遠くまで行ってみよう、場所を変えて自分と家族の時間を見つめ直してみよう、そんな気持ちでした」
そして一人旅で訪れた高知県四万十市。流れる四万十川と、まちの人たちの温かさに触れたそのとき、「ここで暮らす」という選択肢が自然と浮かんだといいます。
「宿の人に“ここ、来ちゃいなよ”って何気なく言われたんですが、不思議とその言葉がしっくりきてしまって。帰りの車内で、もう“移住しよう”って決めてました」
ほどなくして地域おこし協力隊の制度を知り、移住の実現に向けて一歩を踏み出すことに。
現在は、地域資源である休廃校舎の利活用に取り組みながら、地域に開かれたハンバーガーの移動販売を展開。
“暮らしと地域に根を張る”という実感を日々深めています。

福岡県出身。四万十川に惹かれ、家族とともに高知県四万十市へ移住。
地域おこし協力隊として、休廃校舎の利活用プロジェクトに挑戦中。
自然と人に囲まれた暮らしの中で、地域と共に未来を描いている。
松本凌平 |Ryohei Matsumoto @ryohei_matsumoto_1991
MatsumotoBurgerClub @matsumoto.burger.club

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
最初に生まれたのは「四万十で暮らしたい」という気持ちでした。
協力隊になること自体が目的ではなく、移住のための手段として制度を活用しました。きっかけは一人旅です。四万十川を見に来たとき、人の密度の低さや風景の素朴さが自分に合うと感じ、帰る頃には「ここで暮らす」という感覚が現実味を帯びました。
当時は湘南で家族5人の生活。会社員として働き、マンションも購入していました。コロナ禍以降、人が増え、暮らしの速度が自分の感覚とずれてきた実感がありました。妻はセラピストの仕事に踏み出したい、自分はハンバーガーづくりに挑戦したい。けれど湘南で始めるイメージは湧かない。ならば、環境から変えようと家族で合意し、四国の中でも幡多エリアを選びました。知人の紹介で四万十市の協力隊募集を知り、応募したのが始まりです。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
ミッションは休廃校舎の利活用です。
地域側のリサーチと全国事例の調査を並行し、統合で不要になった備品の整理など、現場の作業にも関わります。あらかじめ精密な目標設計があるというより、自由度が高い枠組みのなかで地域と対話しながら組み立てていくイメージです。
並行して、移動式のハンバーガー事業に取り組んでいます。これは個人のなりわいの種であると同時に、活動全体のブースト(底上げ)にもなっています。
食は共通の話題になりやすく、初対面でも会話が起きます。
「どこで出店しているのか」
「食材はどこ産なのか」
そこから地域の情報や人に自然とアクセスが生まれ、休廃校舎の話題へもつながります。
ミッションは休廃校舎の利活用、ハンバーガーは人と情報の流れを加速させる装置。役割を分けて捉えています。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
年次で区切って積み上げるというより、最初に3年間のサイクルを決めました。
柱は3つです。
①コミュニティづくり:休廃校舎やその周辺に足を運び、暮らしの近くにいる人に話を聞く。顔を出す回数を増やし、関係の土台をつくる。
②休廃校舎の利活用の仕組みづくり:地域の状況と全国の事例を見比べ、可能性の方向性を整理する。備品整理など実務も伴走する。
③なりわいづくり(ハンバーガー):移動出店を重ね、地域内外で食材と提供機会の線を張る。
1年目はとにかく地域を知ることに時間を使いました。学校があった場所には必ず暮らしがあり、周辺の方に声をかけると、統合のときの空気や行事の記憶が自然と出てきます。地区の行事や福祉活動にも可能な限り顔を出しました。若い世代の参加が少ない場では、それだけで「来てくれて助かる」と言われます。ハンバーガーづくりはこの時期から動き出し、出店先で「四万十」の話題を交わせる場にもなりました。
2年目も、この3本柱の延長にあります。休廃校舎の現状や備品の棚卸しが進むほど、使い方の可能性が具体の会話になっていきます。ここでもハンバーガーが効きます。出店やSNSでの発信をきっかけに、関心を持った人と会話が生まれ、地域の内外に四万十の情報が広がる。仮説は増えますが、拙速に決めず、地域の理解に合わせて整理していく姿勢を大事にしています。
3年目は、継続できる形の検証です。3本柱を“同時並行で続ける”という初期方針はそのままに、負担のバランスや関わり方の濃淡を見直します。ハンバーガーは週2回の運営を目標にし、収益が安定するほど、活動全体の自由度が高まるはずです。3つは別線ではなく相互に影響し合い、特にハンバーガーは関係を広げるブースターとして働きます。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
市役所に入ることで、地域の情報と人に届く導線が増えました。「この件は誰に聞くと早いか」「この地区にこういう人がいる」といった紹介やマッチングは心強いです。担当の方は忙しく、受け身では進みません。こちらから動き、庁内に顔を出し、近況を共有するほど、次の会話につながります。
コミュニケーションの面では、ハンバーガーの存在が役に立ちます。「あのハンバーガーの人」という共通の話題ができるので、声をかけてもらいやすくなります。制度に頼り切るより、自発的に取りにいくほど支援は厚くなる。現場での実感です。

Q5. 活動地である高知県四万十市の魅力は?
人が少なく、自然が近いことです。混雑を気にせず、自分のペースで動けます。都会のように人口密度が高い場所では、無意識に周囲の速度に合わせてしまいがちですが、ここではそれが少ない。移住前から求めていた感覚に近い環境です。
もう一つは、当たり前の風景の中に残る文化の手触りです。こちらへ来てから「ネイチャーカメラマン」として、自然や人の自然な姿を撮る活動を始めました。SNSで共有すると、「何もない」と言われがちな場所の良さに気づくきっかけになります。外への発信でありながら、地域内での再認識にもつながる。祭りや福祉の場に子どもを連れて参加すると、世代を超えた会話が生まれます。若い世代の参加が少ない場では、それだけで喜ばれ、「来てくれてありがとう」と言われる機会が増えます。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
3つの方向性を明確にしています。
1つ目は、ハンバーガーの週2回運営を安定させること。仕込みと出店のリズムを整え、県内を中心に食材と提供機会の線を太くします。収益が安定すれば、廃校利活用の試行に割ける時間や選択肢が増え、活動全体のブーストになります。
2つ目は、場づくりです。休廃校舎や空きスペースを活用し、食と会話が混ざる小さな場を整えます。内と外の人が交わりやすい設えを、無理のない範囲で探っていきます。
3つ目は、都会から田舎へと越境するサマーキャンプのような学びです。自然と地域の文化に触れる機会をつくり、四万十や高知を知ってもらう入口にしたい。ハンバーガーは窓口となり、写真は記録として残る。3つを循環させる構想です。
課題感としては、地域ごとに存在する独自のルールの見えにくさがあります。理由や流れを知らないと入りづらい。ここを可視化できれば、関わる人の窓口は広がるはずです。休廃校舎の活用と同じく、背景を理解しながら少しずつ言葉にしていくことを意識しています。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
「地域を興す(おこす)ために来る」よりも、「ここに住みたいから来る」を軸にするのがおすすめです。地域を興す主体は基本的に地域の人。外部から来た個人が短期間で地域を変えるのは簡単ではありません。住みたいという意思がはっきりしていれば、協力隊でも就職でも事業でも、選択はぶれません。協力隊の3年間は、地域とつながり、なりわいの種を試すのに向いています。
もう一つは、自分から動き続けること。庁内に顔を出す、行事に参加する、現場に足を運ぶ。小さな動きの積み重ねが、紹介やマッチングにつながります。共通の話題を持つのも効果的です。私にとってのハンバーガーは、活動全体を押し上げるブースターでした。写真の発信も、関心や会話のきっかけになります。完璧な計画に固執せず、3本柱を小さく回しながら、状況に合わせて比重を調整する。迷ったら、人に会いに行く。それで次の一歩が見えてきます。
取材日:2025年7月