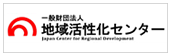Interview隊員インタビュー

ゼロから始める、地域プロモーション
山口県山陽小野田市 林 茂夫さん山口に恩返しをする場所として
「アイ・アム・ア・ジャパニーズ・フロム・チョウシュウ!」
海外で名刺を差し出すとき、林さんはいつもそう名乗ってきました。
かつて侍の時代を終わらせた、小さな長州という土地への誇り。その精神が、異国の地でも彼の背中を押し続けてきたといいます。
高校卒業後に渡豪し、電子部品やITの世界で起業。
複数の国で事業を立ち上げながら、いつか“故郷に恩を返す”という思いを胸に持ち続けてきました。
そんななか、両親の介護をきっかけに帰国。働き口を探すより先に目に入ったのが、「地域おこし協力隊」の募集でした。
選んだのは、山陽小野田市・川上地区。
両親の住む防府市からは車で1時間の場所。
特別に目立つ観光資源があるわけではなく、高齢化が進む80人ほどの中山間の集落。与えられたミッションは「地域プロモーション全般をゼロからつくること」だけ。
だからこそ林さんは、最初の一歩を“企画”ではなく“対話”に置きました。草刈り、祭りの準備、チラシづくり。その何気ない時間の中で、人の顔と地域の呼吸を一つずつ覚えていったといいます。
やがて見えてきたのは、地区に長く受け継がれてきた“地域の方々の人間関係と協力して続けている、地域内の様々な作業”でした。林さんはその姿に、川上の未来を重ねます。

山口県出身。高校卒業後に渡豪し20歳で帰国。半導体商社を起業後、ゲーム、IT、広告分野で6社の起業と50以上の新規事業に携わる。60代を目前にし家族の介護を機にJターン。山陽小野田市川上地区の地域おこし協力隊として、地域全体のプロモーションに取り組む。地域の女性たちが作る「貞任餅(さだとうもち)」の発案、企画、ブランド化をはじめ、ロゴ制作や販路整備、SNS発信などを推進。地域に新しい仕組みを生み出し、持続可能な産業のかたちを模索している。
Instagram
@kawakamichiiki

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
海外で働くあいだも、帰省のたびに地元の元気が少しずつ削れていくのを感じていました。両親の介護が必要になり地元に戻ることを決めたとき、年齢的に山口県での就職は現実的ではない。それならば、地域の課題と自分の経験を直結できる“地域おこし協力隊”に応募しようと考えました。
企画提案やプロモーション、契約渉外、現場の合意形成など、これまでの仕事で培った「新しいことを前に進める技術」を、地元のために使いたかったからです。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
高齢者率65%以上、人口80名弱という川上地区全体のプロモーションです。最初から明確な業務指示はなく、「何をやるかも含めて設計してほしい」という依頼でした。
地域の人口は減り、産業も目立ったものはない。そんな中で、どうすれば地域の存在を知ってもらえるかを常に考えていました。
その一環として取り組んでいるのが、地域の特産品開発です。
まずは、川上地区の小高い丘にひっそりと建てられた平安時代の武将、安倍貞任の塚に着目。
川上地区は、自然の山からの水だけで栽培した餅米の産地でもあるのですが、地域で暮らす70代、80代のお母さんたちがその餅米を使った餅づくりを長年続けてきたことを知り、その餅を安倍貞任の塚と掛け合わせてリブランディングすることを自身の大きなミッションのひとつとしました。
「餅」というありふれた商品をリブランディングするために最初に考えたのが、「時間が経っても固くならない餅を作れないか」ということ。何か手段はないかと調べるうちに、岩手県にある企業「大林製菓」が柔らかい餅作りの技術で特許を取得していることを知り、直接交渉しました。想いに賛同してくれ無事に協力関係をとりつけ、作ってから時間が経っても柔らかく、おいしく食べられる「貞任餅(さだとうもち)」の完成に至りました。
現在は、SNSやローカルメディアのパブリシティを掛け合わせ、川上の“物語を持った餅”として情報発信をしています。
あくまで餅のリブランディングは地域おこし協力隊としてのミッションのひとつ。それだけにとどまらず、地域の中に小さな“誇りの循環”をつくること。そのための実験を、日々積み重ね続けています。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
1年目はとにかく地域に入ることに集中しました。
草刈りや清掃、祭りの準備といった作業を一緒にこなすうちに、雑談が生まれ、相手の素顔が見えてくる。誰が決定権を持っていて、誰が静かに地域を支えているのか。そうした“人の地図”を描くことを優先しました。草を刈る音やお茶休憩の沈黙の間にも、地域のリズムを感じる時間がありました。
2年目は、その中で見つけた“資源”をどう活かせるかを考えました。
地域にある直売所、そして70代・80代の女性たちが続けてきた餅の製造。作る力と売る場所はある。ならば、それをどう磨けば外へ届くか――。
そう考えて、地域ブランディングの柱となる地域ロゴ制作や商品キャラクター開発を東京などの地域外の学校や企業、クリエイター達と進めました。「おいしい」を超えて、「川上らしい」「川上ならでは」と言える価値を探す時間でした。
3年目の今は、事業として次の段階に入っており、貞任餅を海外へ展開する構想を進めています。
生産量が限られるからこそ、価値を高めて単価を上げる。フランスでは餅が一個500円で売れる市場があると知り、次はフランスで貞任餅の餅まきと試験販売をしようと計画中です。
効率よりも“手づくりの価値”で勝負するという、地域らしい挑戦だと思っています。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
一番の支援は「泳がせてくれたこと」ですね。禁止や過干渉ではなく、法や倫理に照らして自制しながら動く前提で、判断を委ねてもらえました。
もう一つ大きいのは、地域の“間に立つ人(コーディネーター)”の存在です。特定の派閥に偏らず、中立に橋渡ししてくれる方がいると、説明や合意形成の摩擦が大きく減ります。特に、自分の言葉を地域の方々が理解しやすいように“通訳”してくれる存在は大きいです。
協力隊側も、その“コーディネーター”に理解、信頼してもらえるように努めることが必要です。どこの地域にも目に見えない人間関係が存在しており、Aさんと仲良くすればBさんに疎まれるなどは発生しますが、どちらかの悪口を媒介に信頼を築こうとしないこと。ネガティブな情報は最後には自分にはね返ってきますからね。
コミュニケーションは日常の文脈で重ねます。雑談のような“余白”で、お互いの性格やペースが見えてくる。そういう時間が、いざという時の合意形成を支えます。

Q5. 活動地である山口県山陽小野田市川上地区の魅力は?
人との距離感と地域の持つ包容力です。困っていると「手伝おうか」と声がかかるけれど、家の敷居を越えてくるような“踏み込み”はしてこない。見守りながら泳がせてくれる。その絶妙さが、挑戦を継続させてくれます。
暮らしの拠点となる住宅も、地域の空き家を選んで地区の“中”に住むことにしました。床が抜け、カレンダーの針が止まった家でも、風呂・トイレ・炊事の導線が確保できれば十分。毎日ムカデやゲジゲジに遭遇しても、地域の“時間”に体ごと触れていたい。仕事帰りにビールを一本。保護猫二匹がひざに乗る。そんな小さな満足が積み重なっています。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
川上地区の事例を、資源も人口も限られた地域の“汎用モデル”にしたいです。
量では戦わず、価値で設計する。デジタルが進むほどアナログの希少性が高まる。だからこそ、手づくりの価値を損なわない販売とブランド運用が要になります。
同時に、これまで約40年間培ったキャリアを活かし、山口県内の起業支援を地道に立ち上げます。契約書の読み解きから店舗運営の基本まで、最初の“つまずき”を減らすだけで生存率は上がる。いずれは「きっかけづくり(カタリスト)」に特化した小さなチームを立ち上げ、各地の挑戦を並走で支えたい。任期後も、山口県の産業・雇用を育てる仕事に関わり続けるつもりです。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
一つ、最初の一年は“地域のための活動以外はやらない”と決めるくらいでちょうどいい。
草刈り、溝さらい、祭りの準備。地味な手伝いに本気で向き合うと、次の扉が開きます。
二つ、常に「〜だからこそ/〜ならでは」を問いにすること。
自分だからこそ、この地域ならでは――この二軸を置き直すと、企画は自然に具体化します。
三つ、最初からボランティアに過度に頼らない。地域の時間と労力を“当てにしない”設計を先に整える。
契約や合意、段取りを固めてから関わってもらう順番が、信頼の貯金になります。
四つ、“間に立つ人”を味方にする。
どんな地域にも、行政と住民の間、住民同士の間に立つ“調整役”のような人がいます。
その人を理解し、信頼関係を築くことができるかどうかで、活動の進み方は大きく変わります。
相手を自分の思い通りに動かそうとするのではなく、一緒に考える。主役は地域の方々であって、自分はあくまでもプロデューサー。中立な姿勢を保ちながら、本音で話し合える関係をつくることが何より大切です。ネガティブな情報を広げず、対話でほぐしていく意識を持ちましょう。
最後に、「立志尚特異(りっしはとくいをたっとぶ)」――我が長州が誇る幕末の思想家・吉田松陰の言葉です。志を立てたなら、人と違うことを畏れてはならない。
言葉にしたことは、小さくてもいいから実行する。その積み重ねが、地域の空気を変えていきます。
やってみればわかります。地域は、思ったよりもちゃんと見てくれています。派手な成果より、約束を守る人のほうを、静かに信じてくれる。その信頼が、自分の足場になります。
そしてもう一つ。
年齢を理由に諦める必要はありません。
これまで積み上げてきた経験や判断力は、地域の現場で確実に生きます。私自身も、協力隊に応募する際に「運転免許がないと難しい」と言われ、59歳で教習所に通いました。何歳からでも、新しいことを始めることで景色は変わります。
同じ世代の誰かが「自分もまだやれる」と思えるきっかけになれば、それがいちばん嬉しいですね。
取材日:2025年10月