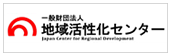Interview隊員インタビュー

岡谷のシルクに物語を織り込む
長野県岡谷市 佐々木千玲さん伝える仕事から、つくる現場へ
東京で映画のPR・マーケティングに長く携わってきた佐々木さんは、仕事の合間に出会った草木染めと機織りをきっかけに、学び直しの道へ進みました。京都で技を身につけるうちに、「素材からきちんと知りたい」という思いが強まり、紹介を受けて長野県岡谷市の製糸工場や機織り工房を見学します。糸の張り具合、道具の置き方、作業の段取り——現場に積み重なる“当たり前”に触れたとき、これまで自分が磨いてきた“伝える仕事”と、これから向き合いたい“つくる仕事”が一本の線でつながったといいます。
「ここなら機(はた)を織れますよ」。そう背中を押され、地域おこし協力隊への応募を決意。
ミッションは「岡谷シルクのブランディングと製品開発」。ブランドコンセプトの言語化、事業プランの設計、WebサイトとSNSの立ち上げを並行しながら、“オール岡谷産”の素材と工程で風呂敷のプロトタイプをつくるため、岡谷蚕糸(さんし)博物館を軸にして地域の養蚕農家・製糸工場・機織り工房の方々に声をかけ、ワーキンググループを組みました。
コロナ禍でイベント開催が難しかった2年目・3年目は、外に広げるより、足元の歴史と工程に向き合い、関係者との対話を重ねて合意の土台を整える時間に振り切りました。任期後は起業し、風呂敷の販売やワークショップ運営、地域の企画運営の手伝い、そして前職の経験を生かしたマーケティング/PRのコンサルティングに取り組んでいます。製品と体験を通じて、岡谷のシルクに今の暮らしの意味を与えていく——そんな姿勢で活動を続けています。

秋田県出身。映画配給会社他でPR/マーケティングに携わった後、京都で草木染めと機織りを学び、長野県岡谷市の地域おこし協力隊に着任。岡谷シルクのブランディングと製品開発を担当、“オール岡谷産”のシルクの風呂敷作りを推進。
卒隊後は製品販売とワークショップ運営を軸に、地域の企画運営やPR支援まで、産地と生活者をつなぐ活動を続けている。
Instagram
@tintt_co

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
京都で草木染めと機織りを学んでいたとき、「織りを続けるなら、まず素材と工程を知ったほうがいい」とアドバイスを受け、製糸業で栄えた歴史がある岡谷に今も残る製糸工場や機織り工房を見学しました。
現場で見たのは、糸が生まれ、布になるまでの流れを支える多くの手と工程です。道具の置き方や手の運び方のような細部にも、長年の蓄積がありました。
その“当たり前”を身体で学びたいと思ったこと、途絶えていた養蚕が復活し、繭と糸の原材料があること、そして「ここで機(はた)を織れますよ」と言われたことが決め手です。前職で培った“伝える”力を、産地の“つくる”現場と地続きにしていきたい——そう考え、地域おこし協力隊への応募を決め、2019年4月に着任しました。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
ミッションは「岡谷シルクのブランディングと製品開発」でした。
初年度からブランドコンセプトの言語化、事業プランの設計、WebとSNSの立ち上げを進める一方、“オール岡谷産”の素材と工程でプロトタイプをつくる構想を固めました。
ブランディングは工程・関係者・歴史を含めた“合意形成のプロセス”だと捉え、行政や地域の皆さんと定義を共有するところから始めました。
これは、日本各地にある「シルクのまち」の中で、岡谷ならではの価値は何か?を共に掘り下げて考えることで、「唯一無二の物語」としてまちの魅力を再認識してもらう工程でした。
その物語を反映する製品として、風呂敷を選びました。性別や年代を問わずに使用できてサスティナブルなアイテムですが、シルクで手織りで作るのはハードルが高く、地域の皆さんとワーキンググループを組んで製品化に取り組みました。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
着任1年目は、養蚕から製糸、織りまでの流れや各工程の担い手、産地の歴史と現在地を把握することを最優先にしました。現場の見学、体験を重ね、人と会って直接話を聞くことで、自分が何を期待されているのかを確かめる時間でもありました。SNSの立ち上げもこの時期に行い、外への発信も開始しましたが、まずは足元の理解と関係づくりを丁寧に進めました。
2年目は、岡谷市ならではの強みや目指す姿を言葉に落とし、関係者が腹落ちできるブランドコンセプトを整えることに集中しました。コロナ禍で移動やイベントが難しく、想定していた予算確保もうまくいかない局面がありましたが、市の担当者の皆さんと企業版ふるさと納税の活用を含めて補助制度の検討・申請を進め、ワークショップやブランド認証制度などのプログラムを事業計画に組み込みました。
自治体側に強かった「ブランディング=何かを作る」という解釈と、私が考える“合意形成のプロセス”としてのブランディングとのズレは、日々の対話の中で丁寧に擦り合わせていきました。岡谷シルクのブランド価値と未来を関係者が共通のイメージとして持てたことが大きな成果だったと思います。
3年目は、合意してきた内容を形にする段階です。岡谷蚕糸(さんし)博物館を軸にして地域の養蚕農家・製糸工場・機織り工房の皆さんとワーキンググループを組んで製品化に取り組み、糸番手や織組織、仕上げ条件をテストしながら“オール岡谷産”の風呂敷のプロトタイプを完成させました。90cm・70cm・45cmの3サイズを用意し、90cmは冬の諏訪湖や八ヶ岳の印象を配色と構成に反映しています。
発表時には地域の方や地元ゆかりの方にも手に取っていただき、「本当に冬の諏訪湖の色に見える」という反応もいただきました。心の奥にあるふるさとの風景や色を想起させる製品ができてほっとしました。完成は終点ではなく、“岡谷シルクの製作工程と、そこに携わる作り手たちの名前が見える起点”だと捉え、その後の販売と学びのプログラムにつなげています。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
所属は岡谷市ブランド推進室(岡谷蚕糸博物館内の一室)で、同じ空間で日常的にコミュニケーションを取りながらチームとして進めることができました。お互い経験してきた仕事のバックグラウンドが違うために理解できないことも起こりますが、自治体側の懐の深さとサポートに助けられました。
内部での情報共有は密にできる一方、視点が固定化しないよう、工房や他地域の協力隊、産地外の専門家とも定期的に意見交換し、外部の声も取り入れてバランスを取るようにしました。
機織り工房の女性たちからは、技術だけでなく、地域の先輩として、人生の先輩として、貴重な知恵をたくさん教えていただきました。

Q5. 活動地である長野県岡谷市の魅力は?
岡谷市は暮らしやすいコンパクトシティです。市役所や病院、映画館、買い物の場所がまとまり、免許のない時期も徒歩と自転車で生活できました。
車の免許を取得してからは、諏訪湖や山並みへの距離の近さをいっそう実感しています。湖面の色と山の稜線は日ごとに表情を変え、製品の色設計でもその変化が手がかりになりました。
この地方は諏訪大社と深いつながりがあり、御柱祭や御神渡りといった自然そのものを崇拝する神事や伝承が暮らしの側にあります。
日常の圏内に自然と歴史が共存し、生活の延長として文化に触れられることが、この地域の大きな魅力です。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
任期中に完成させたプロトタイプの風呂敷を、継続的に届けられる仕組みにしていこうと奮闘中です。
国産の生糸は国内流通の中で0.2%以下という希少な存在で、養蚕や製糸、織りだけでなく、撚糸や精練など各工程の担い手減少により製品作りが非常に難しくなっている現実があります。1枚の布の背後に多くの人の手と時間が積み重なっていることを、製品と体験の両輪で伝えていきたいです。
ワークショップは現在年1回の募集で定員が早々に埋まる状況にあり、今後は提携している工房と相談し、アドバンスコースの設計や、工程見学と手仕事に観光も組み合わせた滞在型プログラムの充実も検討します。大きなことを急がず、関係者の歩幅に合わせて進めることが、結果として産地の裾野を広げると考えています。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
まず、自分が協力隊で「何を得たいか」を一つの言葉にしてみてください。肩書きや成果よりも、3年間で身につけたい視点や暮らしの形がはっきりすると、選ぶ地域や役割が自然と絞れます。ちなみに私は「自然豊かな場所で機織りをして暮らしたい」でした。
そのうえで、募集要項だけで判断せず、現地を歩き、生活の距離感を身体で確かめることをおすすめします。買い物、病院、交通、冬の過ごし方——日常を想像できると、活動の解像度も上がります。
着任後は「全部やろう」とせず、小さく試して、小さく合意を重ねるとうまくいきます。地域には歴史や流れがあり、最初から正解を出すより、耳を澄ませて歩幅を合わせるほうが遠回りに見えて早いです。
孤立しないことも大切です。同僚や先輩隊員、地域の店や工房など、話を聞ける相手を早めにつくっておくと、悩みは小さいうちにほどけます。
年齢や経歴は不利ではありません。これまでの経験は必ず役に立ちますし、学び直しの機会として3年を使う発想で十分です。完璧な準備より、「やりたい理由」と「続けるための暮らし」が見えていれば大丈夫。迷いがあるなら、一度現地の空気を吸いに行く。心が静かに前に動くかどうか——その感覚を大事にして決めてみてください。
取材日:2025年8月