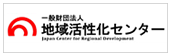Interview隊員インタビュー

安心して集える拠り所をつくる
愛媛県西予市 山口聡子さん東京、香川、愛媛。多拠点の先に見えた「地元」
東京でセラピストとして働いていた山口聡子さん。
忙しさの只中にいた2011年、東日本大震災を機に、暮らしと仕事の距離を見直すようになりました。
「大きな不満があったわけではないんです。ただ、この先を一度立ち止まって考えたい。暮らしにもう少し丁寧に向き合いたい、そう思うようになりました」
それからは東京と出身地である愛媛、家族のいる香川を行き来する多拠点の生活へ。
やがて、地元の先輩の紹介で、出身地である愛媛県西予市が「協力隊を探しているらしい」という知らせを耳にします。実際に地域を歩き、暮らす人の話を聞くなかで、「ここで地域づくりに関わる」という選択肢が自然に浮かびました。
2017年、愛媛県西予市野村地域の地域おこし協力隊に着任。
派手な出来事を追うのではなく、安心して集まれる場所を地域に置く。そんな足元からの実装を、今も淡々と積み重ねています。

愛媛県西予市出身。
東京の大学卒業後、販売職を経てリラクゼーション会社に就職しセラピストに。
多拠点生活ののち、2017年から愛媛県西予市野村地域で協力隊として活動。来訪拠点の運営、放課後子ども教室、有機農業の学びの仕組みづくり等に従事。2018年の西日本豪雨では地域のNPOの副理事長として復旧・復興の受け皿運営に注力。
協力隊修了後は西予市、愛媛県の移住促進・協力隊の中間支援団体勤務を経て、南予移住マネージャーとしてコーディネート業務に関わる。
現在は、(一社)えひめ暮らしネットワークが運営する「COWORKING-HUB nanyosign」の家守としてワーケーションプログラムの醸成にも関わる。
COWORKING-HUB nanyo sign @nanyo.sign

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
はじめから「地域おこし協力隊」という選択肢があったわけではありません。震災後、自分の暮らし方を見直す中で、Uターンという考えはありましたが、当初は東京と地元を往復する多拠点生活を続けていました。東京では、都市と地域を行き来しながら仕事をする人が集うシェアハウスに住み、その実践者たちの姿に触れていました。地域と都会をつないで仕事をつくる。そうした生き方が、自分にもできるかもしれないと思い始めていたところでした。
そんな折、地元・西予市の地域づくり団体が協力隊員を探していると聞きました。地元の先輩の紹介で現地を訪ね、地域の方と一緒に歩いて回り、そこで暮らす人の声に耳を傾ける中で、「ここで地域づくりに関わりたい」という気持ちが固まりました。募集側も、着任後に本人が選べるように幅広い業務を提示してくれていて、やりたいことと地域のニーズを重ね合わせやすいと感じたことも、応募の後押しになりました。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
受け入れは地域づくり団体で、提示されたミッションは幅広いものでした。その中で来訪者の拠点運営、放課後の学び場づくり、若手が有機農業を実践的に学べる仕組みづくりなど、暮らしと仕事の接点作りなどに取り組みました。一次産業から教育、交流まで、日々の暮らしに密着した領域を横断しました。
着任後は、地域のニーズと自身の関心をすり合わせながら、拠点の機能を整え、人が集まり対話できる場を増やすこと、学びの機会を地域内に根づかせることに力点を置きました。着任前から毎月通って話を聞き、期待値を互いに確認していく進め方も、ミッションを実装するうえで大切にしていた点です。日々の暮らしに接する現場感を外さないように進めました。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
1年目は、とにかく“聴く”ことから始めました。着任の半年前から毎月地域に通い、会合に参加して、誰が何に困り、何をやりたいのか、自分に何ができるのかを言語化する。正解を急がず、対話を積み重ねる進め方でした。
並行して、小さな勉強会やイベントを開催したりもしました。テーマは、その時々に地域で話題になっている関心事や、着任後に必要だと感じた学び。東京時代の知人や他地域の協力隊仲間を招くこともあり、内外の人が混ざることで、地域の中に新しい接点が生まれていきました。地域の中に「人が集まって話せる受け皿」を置き、関係人口を増やす土台づくりを意識した1年です。地域外の人に来てもらい、地域の人と混ざる機会を継続してつくることも、当初からの柱でした。
2年目の途中、西日本豪雨により活動拠点と自宅が被災しました。有事下ということもあり、協力隊活動はいったん休止に。地域では外からの支援を受け止める器が必要だったため、地域のNPO「シルミルのむら」の副理事長として、物資・ボランティア・情報の流れを整理し、受け入れや調整を担いました。子どもの居場所づくり、文化財保全のクラウドファンディングなど、その時々の状況に合わせた対応も行っています。行政・地域・支援者の間を「翻訳・調整」し、必要な現場に必要な支援が届くよう動いた時期でした。
3年目は、復興の過程で広がった外部とのつながりを地域の力に変えることに注力。被災で止まっていたプロジェクトを再開し、地域の人たちと一緒に前へ進めました。災害対応で関わったボランティアや来訪者が、イベントや学びの場に再訪し、地域の日常に関与する流れが見えてきました。冊子「ノムライク」では編集を担い、野村の記録と“その後”を残しました。もともと地域の人の元気さを感じていましたが、災害後も「みんなでやっていこう」という空気が失われなかったことが、3年目の推進力になりました。任期の締めくくりとして、拠点運営・学びの場づくり・受け皿整備の3つを通し、地域内に小さくとも継続的に回る仕組みを置くことを意識しました。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
「放置しない伴走」という印象でした。
担当職員や受入団体とは日常的に連絡を取り、LINEやメッセンジャーでのやり取りをベースに、テーマごとに複数の連絡グループ(担当職員と1対1、受入団体のみ、協力隊全体+担当職員など)で情報共有をしました。
地域の会合や顔合わせには必要に応じて同行があり、最初の半年ほどは要所要所で一緒に入ってくれたことも支えになりました。独自の提案にも耳を傾けてもらい、担当職員からも提案をいただいたこともあります。地域側と行政側の視点を行き来しながら進められたことで、「何から手をつければよいか分からない」という状態には陥りませんでした。

Q5. 活動地である愛媛県西予市の魅力は?
包容力と、世代を越えた実行力です。協力隊として関わる中で、子どもからご年配の方まで、立場を超えて地域を良くしようと動く人たちの姿が見えてきました。被災の渦中でも、一度受け止め、前向きにやっていこうとする空気に何度も励まされています。
Uターン者である自分は、出身者としての視点と、外で過ごした後に戻った人の視点の両方を持ち合わせています。“地元のことは半分好きで半分嫌い”、という率直な気持ちも、出身者だからこそ言えて、地域の人にも伝わる。そうした距離感が、翻訳や調整に入りやすい土壌になっていると感じます。関わりしろの多さも魅力です。一次産業、教育、観光、福祉、交流。どの分野にも手が届く余地があり、翻訳と調整の役割が機能すると、小さな協働が次につながっていきます。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
大きな目標を一つに絞るより、「試行錯誤を続けられる状態」を守りたいと考えています。現在は、南予移住マネージャーとして県南部エリアの中間支援に関わり、日本ワーケーション協会の公認ワーケーション・コンシェルジュとして、内子町の「COWORKING-HUB nanyo sign(南予サイン)」を拠点に受け入れや情報の束ねを担っています。
拠点では移住や協力隊の相談の一次受けも行い、その場で人や場を紹介することもあります。また、月に一度のランチミーティングのように、立場の異なる人が安心して話せる小さな場づくりを続けています。食事をしながらの自己紹介や近況共有に加えて、季節に合わせたプレゼント交換や試食会などの小さな仕掛けを入れ、初対面でも自然に話せる空気を整えます。話を聞いて終わりにせず、次に誰と何を試すかまで見えるように設計し、場で生まれた芽を次回へつなぐ。相談は深刻になる前の雑談レベルでも歓迎し、必要に応じて人や場を紹介して橋渡しします。参加者同士が互いを知り、主催者がいなくても交流が回ることを目指す運営は、任期中からの「対話を起点にする進め方」の延長線上にあります。
さらに、翻訳者としての役割も意識しています。行政の立場で大切にしていること、公益性の考え方、制度上できること・できないこと。一方で、協力隊や移住者が抱えがちな戸惑い。双方の言い分を同時に理解し、言いにくいことを言語化して伝える。思いがすれ違わないよう、必要な場に必要な情報を返していく。任期中に行政と長く向き合った経験が、現在の伴走にも生きています。
今後も「その時その場で必要なことを一緒に見つける」姿勢で臨みたいです。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
最初に大切なのは、自分の本当の声を見つけることだと思います。
なぜ協力隊になりたいのか。
なぜ地域で暮らしたいのか。
言葉にしてみると、地域やミッションを選ぶ軸がはっきりします。募集要項の文字だけで判断せず、現地の空気感や、一緒に動く人との相性を必ず確かめてください。できれば複数の関係者と話して、コミュニケーションの取りやすさや、伴走してくれる雰囲気があるかどうかも見ておくと安心です。
Uターンを迷っている方には、出身者ならではの強みも伝えたいです。地域の暗黙知を一から学び直さなくていいこと、帰ってきたことを喜んでくれる人がいること、そして地域と外部の“翻訳・調整役”になりやすいこと。協力隊は年齢や経歴に関わらず挑戦でき、失敗から学べる制度です。私自身、40歳・未経験でもチャレンジの場になりました。3年間という期限は、みんなに平等なチャレンジの時間で、試行錯誤を前提に計画を組み立てやすいです。仲間が増え、関係が広がるほど、次に動ける選択肢も増えていきます。
多拠点で関わり続けて、戻るタイミングを待つのも一つ。人生の優先順位は変わります。
暮らしを軸にしたいと思ったときに制度を使って飛び込む――
そんな使い方も含めて、自分の声に正直に選んでください。外での経験と地元の感覚を併せ持つことは、地元と外をつなぐ役に向いています。迷いながらでも関わり続けること自体が、次の選択肢を広げてくれるはずです。
取材日:2025年7月