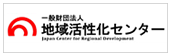Interview隊員インタビュー

ストーリーテリングで旅をつなぐ
北海道北見市 ジャスティン・ランダールさん観光のその先にある「物語」を編む
英語での情報発信とガイドを軸に、地域の物語を掘り起こして伝えていく。
北海道北見市の地域おこし協力隊として活動するジャスティン・ランダールさんは、「観光客が自分の体験を“物語”として持ち帰れるように」と話します。
自分のことを語るよりも、ここに暮らす人や仕事の背景を丁寧に伝える――
そんな姿勢が一貫しています。
「北見そのものがいわゆる観光地と呼ばれることは少ないかもしれません。でも、オホーツクの自然や歴史、カーリング文化、日々の暮らしの中に、伝えるべき物語がたくさんあります」。
派手なコピーではなく、事実に即した言葉で、届くべき相手に届く情報を編んでいく。ジャスティンさんの仕事は、その積み重ねです。

米国出身。大学で歴史学を学び、2019年、23歳で来日。JETプログラムを活用して釧路市教育委員会のALT(英語指導助手)として5年間勤務後、2024年8月より北海道北見市の地域おこし協力隊に着任。英語による情報発信をミッションに、取材・執筆・写真撮影、SNS/Webでの発信、通訳・ガイド、海外向け体験造成や事業者の英語導線整備、ストーリーテリング支援に従事。
Justin Randall @justinarandall_

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
釧路でのJETプログラムの契約が終わる頃から、北海道で暮らし続けたいと考えていました。ちょうど友人から北見市の協力隊募集を教えてもらい、関心を持ったのがきっかけです。
私はフリーランスの記者として新聞や雑誌に寄稿した経験があり、写真撮影もできます。英語で情報を発信し、外から来る人に地域を案内することは、自分のこれまでの経験と重なります。
もう一つは、伝える対象の選び方です。都市部では「オーバーツーリズム」の課題が話題になりますが、人口の少ない地域にこそ、無理のない形で来訪を促す情報が必要です。北見は“有名観光地”のすぐそばにある拠点としてのポテンシャルが高い。そうした「まだ十分に伝わっていない魅力」を英語で紹介したいと思い、応募しました。
来日した日は今でも覚えています。日本語はほとんど話せず、看板も読めませんでした。それでも新しい土地で学び続けることに価値があると感じ、現場で失敗しながら覚えていくことを選びました。協力隊への応募は、その延長線上にあります。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
ミッションは「外国語による情報発信」です。具体的には3つの軸で動いています。
1つ目は、英語での記事執筆と写真撮影、そしてSNSやWebでの発信です。地域の暮らしや仕事の背景、季節の体験を記録し、読者が旅の計画に使える情報として届けます。観光情報に偏らず、地域の日常にある手ざわりを大切にしています。
2つ目は、ガイドと体験のコーディネートです。海外からの来訪者を、農業体験やカーリング体験など、地域の方と出会える現場へつなぎます。2024年度は台湾からのサイクリングツアーで通訳を務めたり、シンガポールからの来訪者のカーリング体験をサポートしたりしました。現場での安全面や英語での説明、移動や食事の段取りなど、運営の“型”も少しずつ整えています。
3つ目は、事業者の海外対応の支援です。英語での情報整備、体験・ツアー商品の磨き上げ、予約・問い合わせの導線づくりなど。「どこで見つけてもらえるのか」「伝わる英語になっているか」を一緒に点検し、足りない要素はストーリー設計から考えます。英文のコピーを整えるだけでなく、写真の選び方、価格や所要時間の表示、キャンセル規定の明記など、基本的なところから確認します。
私が大切にしているのはストーリーテリングです。観光客が“自分の物語の登場人物”として体験できるように、背景の説明や出会いの場を整えることを意識しています。山や湖の美しさだけでなく、そこを守ってきた人の手入れや季節の営みを一緒に伝える。そうすることで、体験は記憶に残りやすくなります。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
1年目は、とにかく地域を学び、歩き、書くことに集中しました。英語の記事を複数執筆し、写真とともに発信。現場でのガイドや通訳も経験しました。北見はオホーツクの各地に近く、例えば屈斜路湖方面へ動くにも拠点性があります。一方で「地域内で体験をどうつくるか」という課題も見えてきました。歴史や文化――ハッカの歴史、オホーツク文化、カーリングなど――を軸に、季節の釣りやカーリング体験など、北見ならではのメニューを整えていく必要を感じています。
2年目は、スキルアップと深掘りの年に位置づけています。動画や写真の撮影・編集をより専門的に。題材も「体験そのもの」だけでなく、その裏側にある人や仕事に踏み込みます。例えば、小さなスキー場の夏場の整備、ドローンを活用する農家の取り組みなど、普段は見えにくい仕事の過程を記録していきます。地域の方に企画段階から入ってもらい、英語の脚本・ナレーションの整備、撮影許可の段取り、公開後の問い合わせ対応までを一連の流れとして設計します。
3年目は、継続性の担保がテーマです。私がいなくなっても続く体験プログラムの運営体制づくり、英語導線の定着、地域側の発信力の底上げを目標にします。受け入れ人数や保険、料金設定、緊急時の連絡手順、英語の安全説明書など、運営に必要なチェックリストを整える計画です。あわせて、米国の大学と連携して、歴史や食(ガストロノミー)を学ぶ短期留学・フィールドスタディの受け入れ企画にも挑戦したい。地域の方に講師やホストとして関わってもらい、現場での学びを英語で共有できるように準備します。
個人としては、より影響力のある媒体で記事を書く機会を広げること、地域の短編ドキュメンタリーを継続的に制作することも3年目の到達点に置いています。量と質の両方を意識し、実績を積み上げる年にしたいです。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
市役所の上司や担当の皆さんから、日々フィードバックをもらっています。
アイデアに対して「ここは良い」「ここは改善したい」と具体的に返してくれるので、次のアクションへ繋げやすいです。英語話者は多くありませんが、こちらの日本語が拙い場面でも、意味が伝わるまで丁寧に向き合ってくれます。時間をとって説明してもらえることは、とても助けになります。
申請や手続きが必要な局面では、担当部署を紹介してもらい、関係者に適切に繋いでもらいました。現場での受け入れ調整や、連絡先・施設利用のルールの共有など、土台となる部分を整えてもらえたことは大きかったです。
同時に、協力隊としての自立も大切だと考えています。生活手続きや細かな問題解決は、まず自分でやってみる。必要なところで相談する。このバランスが、受け入れ側との信頼につながっていると感じます。自分で調べ、言葉にして相談することが、結果的に仕事を前に進める近道になりました。

Q5. 活動地である北海道北見市の魅力は?
一言でいえば、「自然が生活に近いこと」です。北見から1時間圏内で、多様な自然にアクセスできます。食べ物はおいしく、家賃も比較的抑えられていて、暮らしの基盤がつくりやすい。加えて、人と人の距離が近いと感じます。初めて会っても、すぐに打ち解けられる人が多いです。
印象に残っている出来事があります。道東で活動する協力隊の先輩と、SNSをきっかけに街のカフェで初対面しました。お互いの仕事や関心を話すうちに自然とつながり、今では地域をまたいだコラボレーションが生まれています。フリーランス同士は競合になりがちですが、ここでは協力のほうが成果につながる。そんな空気があります。
歴史や文化の層の厚さも魅力です。ロコ・ソラーレの活躍で知られる北見のカーリング文化や、オホーツク文化の痕跡、ハッカなど産業の歴史。「観光名所」という括りではなく、日常の仕事の場に物語がある。雪の季節に向けて地域の方が手を入れ続けるからこそ守られている景観も多い。こうした背景を知ると、同じ場所でも見え方が変わります。
暮らしの面でも、若い世代が集まる場がいくつかあり、季節の遊びを一緒に楽しむ文化があります。互いの得意分野を持ち寄ってイベントを組み立てたり、小さく試して改善したり。過度に背伸びをせず、手の届く範囲で積み重ねていく雰囲気が、居心地の良さにつながっています。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
個人としては、プロのジャーナリストとしての活動を確立したいです。地域の経済や政策、まちづくりの現場を、英語でわかりやすく伝える記事や写真、短編ドキュメンタリーを継続的に出していきます。扱うテーマは、「地域おこし」の現場で実際に起きていること。企画の狙い、実施のプロセス、費用や効果、継続の壁――結果だけでなく過程を記録し、読み手の判断材料になる情報を届けたいと考えています。
地域としては、教育分野との連携を強めたいです。海外大学の短期留学を受け入れ、北見を拠点に歴史や食、産業を学ぶプログラムをつくる。受け入れ先の安全管理、交通手段、英語での講義や現場解説、レポート課題の設計、評価方法まで含めて、大学側と共有できる仕様書を整えるのが目標です。地域の事業者や研究者に講師として参加してもらい、任期後も継続できる形に育てます。
また、体験商品の磨き上げと可視化にも取り組みたいです。英語サイトや予約ページの表記統一、写真のアップデート、よくある質問の整理、支払い・キャンセルの導線整備など、基本を整えるだけで情報が届く範囲がより広がります。地域の方が自走できるように、チェックリストとテンプレートを作り、ワークショップ形式で共有していく予定です。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
外国人向けとしては、まず、日本語です。高度な表現は不要でも、生活や仕事上の問題を自分で解決できるレベルは必須だと思います。手続きや契約内容の理解、現場での意思疎通を他人任せにしないことが、信頼につながります。
次に、外向きの姿勢。現場に出て、人に会い、話を聞く。ネットワークづくりはこの仕事の土台です。最初から完璧な企画を持ち込む必要はありません。小さく関わり、小さく改善を重ねることで、地域のニーズと自分の強みが重なる点が見えてきます。会議室で考えるより、現場で試したほうが早い場面が多いです。
伝え方の軸は「自分」ではなく「地域の物語」に置くこと。インフルエンサー的な自己発信が悪いわけではありませんが、協力隊の役割は、地元の人や仕事の背景を可視化し、任期後も続く仕組みに落とし込むことだと考えています。体験プログラムや情報導線、英語対応のマニュアルなど、“残るもの”を意識して動く。最後は一人で抱え込まず、チームをつくる。分担と連携ができると、企画は長持ちします。
さらに付け加えるなら、「巻き込む力」を意識すると更にいいですね。地域の方、行政、事業者、外からの来訪者など、関わる人が多いほど、企画は柔軟になります。合意形成には時間がかかりますが、手順を言語化し、役割と期限を明確にするだけで前に進みます。自分の意見を通すより、目的を共有し、選択肢を並べ、納得解を探す。その積み重ねが信頼を生み、次の企画の呼び水になります。
最後に、自分の生活を整えること。住まいや健康管理、移動手段、情報収集の方法を早めに固めておくと、現場に時間を使えます。小さな不安を放置せず、先に片付ける。安心して動ける土台があると、出会いに集中できますよ。
取材日:2025年8月