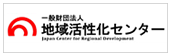Interview隊員インタビュー

“行きつけの田舎”をつくる
長野県辰野町 小菅勇太郎さん長野県の小さな里山に生まれた“行きつけの田舎”
長野県辰野町。
南アルプスと中央アルプスに挟まれた小さな町に、一軒の古民家を拠点にした宿泊施設があります。
名前は「Co-sato(コサト)」。
都会の家族が訪れ、近くの川で遊び、田んぼで泥にまみれ、ヤギに餌をやる。そんな田舎ならではの一日が体験できる場所です。。
運営しているのは、小菅勇太郎さん、24歳。
東京で大学生活を送っていた頃に辰野町と出会い、やがて二地域居住をスタート。20歳で起業し、2022年4月から2025年3月までの3年間、地域おこし協力隊として活動しました。
「誰かにとっての“行きつけの田舎”をつくりたいんです」
そう話す小菅さんは、辰野町を拠点にしつつ、東京や他地域とも行き来する複数拠点生活を送っています。
制度に依存するのではなく、制度を使いこなす。その3年間で培った経験は、今も事業の基盤として息づいています。

東京出身。大学在学中に長野県辰野町と出会い、地域おこし協力隊の制度を活用して起業。
現在は「行きつけの田舎のあるライフスタイル」をつくる宿泊施設「Co-Sato」を運営。
拠点の拡大を視野に、地域の未来を描いている。
Co-Sato (こさと) | 子連れ家族向け・体験型宿泊施設 @cosato_official

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
辰野町に通い始めたのは大学時代です。東京に住みながら、関係人口としてイベントや活動に関わっていました。
辰野町のおじいちゃんたち15人ほどの前で「若者が集まる拠点をつくりたい」とプレゼンしたら、「空いている家があるよ」といくつも古民家を紹介してもらったんです。今の拠点も、そのときのご縁で出会いました。
もともとは起業を目的に辰野町に拠点を持ちましたが、20歳での挑戦に周囲は心配してくれて、役場が柔軟に相談に乗ってくれました。2022年4月に住民票を辰野町に移して着任し、制度を活用しながら事業の土台を築くことができました。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
里山資源を活用したビジネスモデルの創出がミッションでした。
辰野町の川や森、農地は、すべてが生活の延長線上にあり、歩けばすぐ自然に触れられる距離感です。その環境を活かして町外から人を呼び込み、交流人口や関係人口を増やしていくことが大きなテーマでした。
活動の中では、単に観光客を増やすことではなく、「この町と長く関わりたい」と思ってもらえる仕掛けづくりを大切にしていました。たとえば、地元の人と一緒に田植えや稲刈りを体験してもらったり、川遊びや里山散策を案内するだけでなく、その後も季節ごとに再訪したくなるようなつながりを作る工夫をしていました。
さらに、自然だけでなく、そこに暮らす人の魅力も伝えることを意識していました。農作業の知恵を持つおじいちゃん、おばあちゃんや、新しく移住してカフェを開いた若い世代など、地域の多様な人たちを紹介することで、「自然も人も温かい町」という印象を育てていったんです。そうして築いた関係は、イベントや宿泊事業へと自然に広がり、ビジネスとしても持続可能な形に近づけていきました。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
1年目は、協力隊本来の業務を幅広く担当しました。
特に印象的だったのが「かわしま地域新聞」の発行です。これは地域内で回覧板のように配布される手作り新聞で、移住者や地元の方を取材して紹介するもの。お互いの暮らしや活動を知るきっかけをつくり、地域内のつながりを深めることを目的にしています。もともとは先輩の協力隊員が始めた取り組みで、その役割を引き継ぎました。
そのほか、地元の田んぼを活用したスポーツイベントの運営、企業誘致のためのプレゼンとアテンドなど、関係人口創出につながる業務を幅広く経験。並行して、親子向けの体験イベントを試験的に実施し、今の宿泊事業につながる手応えを得ました。
2年目からは起業型の地域おこし協力隊に移行。「Co-Sato」を正式にスタートさせ、顧客ヒアリングとサービス改善をひたすら繰り返しました。東京の公園で風船とチラシを配ることもあれば、子育てコミュニティと連携してモニター宿泊を行うこともありました。
3年目は、クラウドファンディングと借入を活用して施設を大幅に改修。水回りや空調など、快適に過ごせる環境を整えました。その後は口コミやリピーターを軸に集客し、複数家族が一緒に泊まるスタイルを定着させました。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
20歳で東京との二地域居住をしながら起業を志している私に対し、役場の方が親身に相談に乗ってくれ、協力隊になることを後押ししてくれたことは本当にありがたかったです。結果、協力隊として辰野町への移住を果たすことができました。
そして2年目からの活動内容の変更も役場が柔軟に動いてくれたおかげで、起業を前提とした活動が実現できました。着任当初は右も左も分からない状態でしたが、事業の検証段階では役場職員や他の協力隊員が積極的に手を貸してくれ、イベント運営や集客の面でも大きな助けとなりました。
さらに心強かったのは、地域の方々からの支えです。例えば、空き家探しの際には複数の古民家を紹介してくださり、農地や施設の利用についても地元の方が間に入って調整してくれました。地域内でのつながりが広がると、イベントに必要な資材の貸し出しや、人手が足りないときのボランティア参加など、自然と協力が集まるようになりました。
資金や経験が限られていても、こうした人的ネットワークや地元の信頼関係があることで、挑戦のハードルは大きく下がります。単に制度のサポートを受けるだけでなく、地域全体で「この取り組みを応援しよう」という空気があったことが、活動を続けられた大きな理由でした。

Q5. 活動地である長野県辰野町の魅力は?
自然と人、その両方です。
辰野町川島地区では、80歳を超えるおじいちゃんたちが、草刈りや水路の手入れを欠かさず続けています。夏の朝、まだ日が高くなる前から鎌を手に動く姿は、この町の暮らしの一部です。「この景色は当たり前じゃないから」と言われたとき、東京で暮らしていた頃にはなかった感覚に気づきました。景観は自然に残るものではなく、誰かの手で守られ続けているからこそ存在するのだと実感しました。
さらに、ここ数年は若い移住者も増えています。古民家を改装してカフェや雑貨店を開く人、地域の特産品を活かした小さな工房を始める人など、新しい風が次々と吹き込まれています。そうした挑戦に対して、地元住民が温かく受け入れ、応援してくれる空気があることも辰野町の魅力です。外から来た人と昔から住む人が混ざり合いながら、新しい文化が少しずつ育っている場所だと思います。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
現在は協力隊の任期を終え、引き続き「Co-Sato」を拠点に活動を続けています。宿としての運営はもちろん、地域の人やリピーターと一緒に新しい体験プログラムを作るなど、より深く町と関わる動きも進めています。
今後は、このモデルを辰野町だけにとどめず、他の地域にも広げていきたいと考えています。起業当初から複数拠点展開の構想は持っていましたが、実際に運営してみると、地域ごとの特性を理解し、信頼関係を築き、事業として成り立たせるには予想以上の時間と手間がかかることを実感しました。そのため、まずは辰野町での成功事例を確立し、次に移す際のモデルケースとして活用できる形に整えています。
将来的には、日本各地に“行きつけの田舎”を増やしたいです。都会と地方を行き来するライフスタイルがもっと当たり前になれば、都市に住む人も地方に住む人も、互いの暮らしの魅力を享受できるようになります。そのためにも、ただ宿を増やすのではなく、その土地らしさを体感できる体験や、人との関係が継続する仕組みを生み出したいと思っています。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
自治体によって、協力隊活動の自由度や活動内容は想像以上に大きく異なります。事業のテーマや予算の使い方、活動の裁量権などは、同じ協力隊制度でも自治体ごとにまったく違うので、まずはその地域の空気感や方針を知ることが大事です。辰野町の場合は特に自由度が高く、やりたいことを提案すれば柔軟に受け止めてもらえる環境がありました。私にとっては、それが大きな挑戦の後押しになりました。
3年間、一定の収入を得ながら挑戦できる環境は、本当に貴重です。ただ、与えられた期間だからこそ、受け身で過ごしてしまうとあっという間に終わってしまいます。能動的に動き、まずは小さなことでも試し続けることが大切です。私は地域のイベントや空き家活用の現場に積極的に顔を出し、地元の人や移住者とのネットワークを広げることから始めました。
また、任期後を見据えて活動する視点も欠かせません。3年目になってから慌てて準備するのではなく、最初から「卒業後にどうなっていたいか」を考えて行動すると、成果や人脈の積み重ね方が変わってきます。制度はあくまで手段であり、自分のやりたいことを叶えるための舞台装置。そう割り切って、期間を最大限活かしてほしいと思います。
取材日:2025年5月