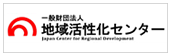Interview隊員インタビュー

「手と手」で「場」をつくる
長崎県五島市 村野麻梨絵さん結婚式をつくりたくて、島に渡った。
東京のアパレルブランドでプレスやグラフィックデザインに携わっていた村野麻梨絵さん。
満員電車に揺られる日々のなかで、「人の幸せな一日を、たくさんの人が関わってつくり上げる」結婚式の現場に惹かれました。
祖父母の住む五島を思い浮かべ、「ここなら、自分の手で式をつくれるかもしれない」と感じたことが、地域おこし協力隊への応募につながります。
2015年、長崎県五島市へ移住。配属先は市役所の観光物産課。任務は、修学旅行生の受け入れを目的とした民泊事業の推進でした。
受け入れ家庭への説明や申請手続きの支援、保健所・消防との調整、必要に応じた現場確認への立ち会いなど、立ち上げ期の現場を走り回る日々。
各家庭を訪ね、設備や衛生面を一緒に確認しながら、安心して子どもたちを迎えられる体制づくりを支えていきました。
任期の終わりが見えてきた2018年1月、カフェ「te to ba(手と場)」をオープン。
のちに宿、ウェディング、そして小さな美術館へ。いまは合同会社 te to ba の代表として、「住み続けられる島」を掲げ、日常に根づく営みを淡々と続けています。
聞こえてくるのは大きなスローガンではなく、ひとつひとつの仕事を丁寧に積み重ねる姿勢。協力隊の3年間で築いた関係と視点が、いまの“場づくり”の原点になっています。

埼玉県出身。東京でアパレルブランドのプレス/グラフィックデザインを手がけたのち、2015年に地域おこし協力隊として長崎県五島市へ。修学旅行民泊事業の推進やハンドメイドマーケットを通じて地域の手仕事に触れ、2018年にカフェ「te to ba 〈手と場〉」を開業。現在は宿やウェディング、美術館の運営を行いながら、「住み続けられる島」をテーマに、暮らしと文化をつなぐ活動を続けている。
Instagram
@te_to_ba

Q1. 地域おこし協力隊に応募したきっかけを教えてください。
アパレルでプレスの仕事をしていた頃、個人の仕事としてウェディングドレスをつくる機会がありました。
結婚式は、多くの人が関わって一日をつくる現場です。その仕事に本気で関わりたいと思ったとき、東京ではなく祖父母のいる五島が頭に浮かびました。
五島市の情報を集めていた時、ちょうど協力隊の募集があり、迷わず応募しました。五島なら、結婚式を起点に人の手が集まる「場」をつくれる。そう感じたのが出発点です。
Q2. 協力隊の活動ミッションを教えてください。
当時の五島市は、近年のようないわゆる「ミッション型」ではなく、市役所の観光物産課に配属され、修学旅行生の民泊事業の推進を行うことが主な業務でした。
受け入れ家庭を訪ねて説明会を行い、申請書類の作成を手伝い、保健所や消防との調整を行う。いわば、事業の立ち上げを支える“伴走役”でした。
机に向かう時間よりも、地域の家を一軒ずつ回る時間の方が長かったように思います。
立場は自治体職員でも、日々の現場はまさに地域そのものでした。

Q3. 活動1年目、2年目、3年目の計画はどのような内容でしたか?
1年目は民泊の立ち上げに奔走。申請手続きや許可取得を手伝いながら、地域の暮らしに深く入り込みました。
民泊家庭での会話の中から、「この人はこんなものをつくっているんだ」という意外な気づきが次々と生まれ、手しごとの多さに驚かされました。
2年目は、そうした「手」を前に出す場づくりとして、ハンドメイドマーケットを開催。
最初は数人から始まり、回を重ねるごとに出店者が増えていきました。この取り組みを機に「手づくりを売ること」に挑戦する人が増え、島の中で小さな経済が動き出す感覚がありました。
終盤には、商店街でファッションショーを企画。ALTや高校生をモデルに、地域の人がつくった服を着て歩くというものです。
地元の美容師組合がボランティアでヘアメイクを担当し、地域の商店街全体が一体となるイベントになりました。翌日の長崎新聞に大きく掲載され、反響も大きかったです。
3年目は、任期後の自立を見据え、業務の効率化を図りながらカフェの開業準備を開始しました。
上司と相談して時間を調整し、週末には空き家の片付けや改修を進め、2018年1月にカフェ「te to ba 〈手と場〉」をオープンしました。
カフェは、地域の人がふらりと集い、話し、ものを作る“居場所”のような存在にしたいという思いから始まりました。
その延長で、島を訪れる人にもっと深く五島の暮らしを体験してもらいたいと考え、カフェとは別の物件を改修して、徒歩圏内に宿を開業。
観光というより、日常の中に滞在してもらうことを目的にしています。
また、協力隊のきっかけでもあったウェディングは、五島の自然と地域の人々の手を活かした“手づくりの結婚式”として少しずつ形になっていきました。
教会ではなく浜辺やカフェなど、島の日常を舞台にするスタイル。関わる人たちの“その人らしい時間”をみんなで作るという試みです。
そして2025年、「てとば美術館」を開設。
島の手仕事や記憶を残し、次世代へ伝えるための場として立ち上げました。
展示だけでなく、子どもたちが地域の文化やものづくりを学べるプログラムも構想中です。
Q4. 活動中、自治体・受入団体からはどんなサポートがありましたか?
私が就任した2015年頃は、五島市での地域おこし協力隊に関する各制度がまだ十分に整っていなかったため、明確な支援制度はありませんでした。
ただ、上司と何度も話し合い、「任期後に生きていけるような計画を立てたい」と提案し、柔軟に動ける環境をつくってもらいました。
仕組みがないからこそ、対話で道を開く。そうした経験が、今の事業を進める上でも役立っています。

Q5. 活動地である長崎県五島市の魅力は?
五島の一番の魅力は、人の距離が近いことです。
車ですれ違う相手の顔がわかる、商店街で声をかけられる。
最初は少し緊張しましたが、「見られている」ことが安心にもつながっていきました。
また、民泊で関わった“五島の家庭の暮らし”から、手仕事が自然に息づく文化に出会えたことも大きいです。
その延長に、今のカフェや宿があります。
Q6. 今後、取り組んでみたいことを教えてください。
「住み続けられる島をつくる」。
カフェ、宿、ウェディング、美術館――これまで手がけてきた事業は、いずれもその理念をかたちにしたものです。
食や滞在、祝い、文化といった暮らしの単位を通して、五島の良さを外にも内にも伝える場をつくってきました。これからは、その延長線をさらに深めたいと考えています。
まずは、地域の人の手仕事や記憶を記録し、次世代に手渡すための取り組み。
美術館を拠点に、子どもたちが島の行事やものづくりを学べるプログラムを整えたいと思っています。
また、島の外と中をつなぐ「五島版レジデンス・プログラム」を2025年から進行中です。アーティストや職人、デザイナーが滞在し、地域の人と共同制作を行う。その過程を展示や商品づくりにつなげるような試みです。
もうひとつは、経済の循環を意識した仕組みづくり。
文化活動を続けるためには、持続的に収益を生む必要があります。助成金に頼らず、雇用や販売を通じてお金が地域内を回る構造を整えること。「稼ぐこと」と「残すこと」を両立させたいと思っています。
「te to ba 〈手と場〉」は、私一人の店ではなく、地域やお客さんが自然に関わる“共有の場”になりつつあります。
これからもこの“場の力”を使いながら、五島をもっと誇れる場所にしていきたい。
暮らしの延長に文化があり、文化の延長に経済がある――そんな循環を少しずつ形にしていきます。

Q7. 地域おこし協力隊への応募を検討している人にアドバイスを!
まずは候補地に行ってみてください。昼だけでなく夜の時間も。
人の会話や空気の距離感に、その地域の性格が表れます。そのうえで「ここで暮らしたい」と思える場所を選ぶことが大切です。
次に、最初の一年は“聞く”に徹すること。都会での経験を活かすのはそのあとでいい。
地域の人の話を聞き、背景や文脈を理解してから提案する。上から目線の改革は長続きしません。
そして、応援してくれる人を見つけること。
全員に好かれる必要はありません。けれど、一人でも味方がいれば続けられます。プレッシャーを感じたとき、相談できる相手の存在は大きな支えになります。
協力隊の3年間は、地域の中に入るための貴重な時間です。名刺一枚で家に上がり、暮らしに触れ、関係を築ける。その経験をどう使うかで、卒業後の生き方が大きく変わるはずです。
取材日:2025年8月